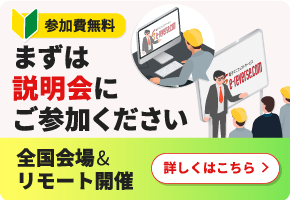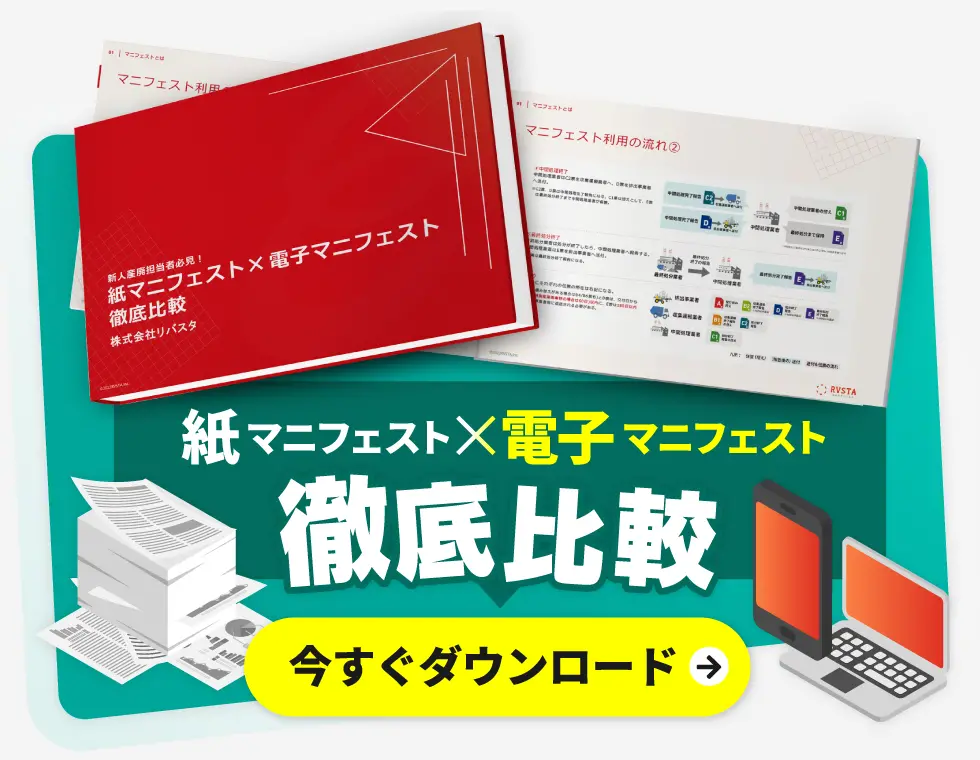私たちが生きていく上で、必ず出してしまうさまざまなゴミ。これらのゴミは正式には廃棄物と呼ばれ、その扱いや処理の方法に細かいルールが定められていることがほとんどです。特に事業を推進していく中で多くの廃棄物を排出してしまう事業者の場合、廃棄物とは何か、またそれらをどのように扱わなければならないかを正しく理解しておかなければなりません。廃棄物について、その分類や処理の流れなどについて、詳しく解説していきます。

お役立ち資料
「産廃担当者が知るべき廃棄物処理法」を1冊にまとめました
新しく産廃担当者となった方向けに、廃棄物処理法を中心に知っておくべきことを簡単に紹介します。
PDFで詳しく見る
目次
01廃棄物の分類 (産業廃棄物と一般廃棄物の違い)
事業活動で出る廃棄物であっても、廃棄物の種類や排出した企業の業種によって産業廃棄物なのか一般廃棄物なのか変わります。
産業廃棄物
一般的にゴミと呼ばれる廃棄物には、大きく分けて「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の2種類があります。
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、廃棄物処理法で定義された20種類の廃棄物のことです。
代表的なものでは、石炭がらや焼却炉の残灰などの「燃えがら」、鉱物性油や動植物性油などの「廃油」、鉄鋼または非鉄金属の破片や研磨くずなどの「金属くず」などが挙げられます。
また産業廃棄物の中でも、爆発性や毒性があり人々の生活に危険を及ぼすものについては「特別管理産業廃棄物」と呼ばれ、その扱いは特に注意しなければなりません。
ちなみに、産業廃棄物には量に関する規定がないため、排出量がごく少量であったとしても産業廃棄物として認定されます。例えば個人事業者のように事業規模が小さく、排出する廃棄物が極めて微量であったとしても、産業廃棄物としてしっかりと対応・処理していかなければなりません。
一般廃棄物
一般廃棄物とは、上記で解説した産業廃棄物以外の廃棄物のことです。さらに一般廃棄物は、事業活動によって生じる「事業系一般廃棄物」と、一般家庭の日常生活から生じる「家庭系一般廃棄物」、さらに爆発性や毒性を持った「特別管理一般廃棄物」の3種類に細分化されます。


お役立ち資料
PDFで詳しく見る
02産業廃棄物の種類
産業廃棄物は、廃棄物処理法で定義された20種類の廃棄物のことを指します。
| 種類 | 具体例 | |
|---|---|---|
あらゆる事業活動に伴うもの |
1.燃えがら | 石炭がら、灰かす、廃棄物焼却灰、炉清掃掃出物、コークス灰等 |
| 2.汚泥 | 製紙スラッジ、下水汚泥、浄水場沈でん汚泥、中和沈でん汚泥、凝集沈でん汚泥等 | |
| 3.廃油 | 潤滑油系廃油、切削油系廃油、洗浄油系廃油、絶縁油系廃油、圧延油系廃油等 | |
| 4.廃酸 | 無機廃酸、有機廃酸、アルコール発酵廃液、アミノ酸発酵廃液、エッチング廃液等 | |
| 5.廃アルカリ | 洗びん用廃アルカリ、石炭廃液、廃灰汁、アルカリ性めっき廃液、廃ソーダ液等 | |
| 6.廃プラスチック類 | 廃ポリウレタン、廃スチロール、廃ベークライト、廃農業用フィルム、各種合成樹脂系包装材料のくず等 | |
| 7.ゴムくず | 切断くず、裁断くず、ゴムくず、ゴム引布くず、エボナイトくず等 | |
| 8.金属くず | 鉄くず、空かん、古鉄・スクラップ、ブリキ、とたんくず等 | |
| 9.ガラス・コンクリート・陶磁器くず | 廃空ビン類、板ガラスくず、インターロッキングくず、石膏ボードくず、土器くず、陶器くず等 | |
| 10.鉱さい | 高炉、平炉、転炉、電気炉からの残さい等 | |
| 11.がれき類 | コンクリート破片、レンガ破片、ブロック破片、石類、瓦破片、その他これに類する各種廃材等 | |
| 12.ばいじん | 電気集じん機捕集ダスト、バグフィルター捕集ダスト、サイクロン捕集ダスト等 | |
排出する業種が限定されるもの |
13.紙くず | 印刷くず、製本くず、裁断くず、旧ノーカーボン紙等、建材の包装紙等 |
| 14.木くず | 建設業関係の建物、橋、電柱、工事現場、飯場小屋の廃木材等 | |
| 15.繊維くず | 木綿くず、羊毛くず、麻くず、糸くず、布くず等 | |
| 16.動物系固形不要物 | と蓄場において処分した獣蓄、食鳥処理場において処理した食鳥 | |
| 17.動植物系残さ | ・魚・獣の骨、皮などの動物性残さ・ソースかす、しょうゆかす、こうじかすなどの植物性残さ | |
| 18.動物のふん尿 | 牛、馬、豚、めん羊、にわとりなどのふん尿 | |
| 19.動物の死体 | 牛、馬、豚、めん羊、にわとりなどの死体 | |
| 20.コンクリート固形化物など、上記の産業廃棄物を処分するために処理したもので、1~19に該当しないもの | ||
産業廃棄物一覧表では産業廃棄物の種類を大きく「あらゆる事業活動に伴うもの」と「排出する業種が限定されるもの」に分けています。これにより、例えば製紙工場から排出される紙くずは「産業廃棄物」になりますが、飲食店などから排出される紙くずは「一般廃棄物」となるなど、業種によって廃棄物の扱いが変わるケースも出てくるため注意しましょう。

お役立ち資料
PDFで詳しく見る
03産業廃棄物の処理の流れ
産業廃棄物を処理する際は、「収集・運搬」「中間処理」「最終処分」の3つのステップを踏まなければなりません。
収集・運搬
排出された産業廃棄物を適切に処理できる場所に持って行くために、産業廃棄物を収集し、運搬することを総称して「収集・運搬」と呼びます。
排出事業者が自ら収集・運搬を行う場合に必要な許可は特にありませんが、他の業者から委託を受けて収集・運搬を行う場合は、専用の許可を得なければなりません。またこれらの許可は、主に都道府県が担当しており、例えば荷積みと荷卸しの場所が都道府県をまたぐ場合、それぞれの都道府県から許可を得る必要があります。
中間処理
産業廃棄物の最終処分を行うために、分別を行ったり、粉砕による減量化を行ったり、脱水、焼却・中和等を行うことを、総称して「中間処理」と呼びます。産業廃棄物そのものの量を減らしたり、再利用可能な資源にしたりすることができるため、産業廃棄物の処理の中でも特に大切なステップと言えるでしょう。
最終処分
中間処理を終えた産業廃棄物を、土の中に埋めたり、海に投棄することを「最終処分」と呼びます。 最終処分を行うことができる土地には限りがありますし、新たな土地を開拓する際にも周辺の住民から理解を得るのは簡単なことではありません。どうすれば排出量そのものを減らせるか、どうすれば中間処理で産業廃棄物の量を減らせるか、といったことを検討し、改善をはかっていくことも、排出事業者に与えられた役割と言えるでしょう。

お役立ち資料
PDFで詳しく見る
04産業廃棄物の比重
産業廃棄物の最終処分量に応じて課税される産業廃棄物税や、収集運搬業者に委託する際の料金など、産業廃棄物に関わる金額の計算は産業廃棄物の重さを基準にするのが一般的です。
しかし産業廃棄物の種類は多種多様であり、ものによってはその性状から、重量を求めるのが困難な場合も少なくありません。
そこで用いられるのが、産業廃棄物の比重という考え方です。産業廃棄物の比重では、1立方メートルあたり1トンという基準から、それぞれの産業廃棄物ごとに割り当てられた換算係数をかけることで、そのおおよその重さを算出します。
産業廃棄物それぞれの換算係数は以下の通りです。
| 廃棄物の種類 | 換算係数 | 1立方メートルあたりの重さ |
|---|---|---|
| 燃え殻 | 1.14 | 1,140kg |
| 汚泥 | 1.10 | 1,100kg |
| 廃油 | 0.90 | 900kg |
| 廃プラスチック類 | 0.35 | 350kg |
| 紙くず | 0.30 | 300kg |
| 木くず | 0.55 | 550kg |
| 繊維くず | 0.12 | 120kg |
| 動植物性残さ | 1.000 | 1,000kg |
| ゴムくず | 0.52 | 520kg |
| 金属くず | 1.13 | 1,130kg |
| ガラス陶磁器くず、コンクリートくず及び陶磁器くず | 1.00 | 1,000kg |
| がれき類 | 1.48 | 1,480kg |
| 建設混合廃棄物 | 0.26 | 260kg |
| 管理型混合廃棄物 | 0.26 | 260kg |
| 安定型混合廃棄物 | 0.26 | 260kg |
| 感染性廃棄物 | 0.30 | 300kg |

お役立ち資料
PDFで詳しく見る
05事業者にかかる基準
産業廃棄物を排出する事業者が、その産業廃棄物を処分したり保管したり、別の業者に委託する場合、それぞれ廃棄物処理法で定める「処理基準」「保管基準」「委託基準」に従わなくてはなりません。
処理基準
産業廃棄物の処理基準には、大きく分けて、産業廃棄物の収集・運搬の方法に関する「収集運搬基準」と、処分の方法に関する「処分基準」の2種類があります。
収集運搬基準
産業廃棄物の排出事業者が、自ら産業廃棄物の収集・運搬を行う場合に義務付けられている基準で、代表的なものに以下のようなものがあります。
- 廃棄物が飛び散ったり、漏れ出したりしないようにする。
- 悪臭や騒音、振動などに対して必要な措置を講じる。
- 運搬車の外側に「産業廃棄物収集運搬者」であることを表示する。
- 運搬車に、事業所の名称や連絡先、運搬先の所在地、産業廃棄物の種類などを記した書類を携行する。
保管基準
産業廃棄物の排出事業者が、収集・運搬や処理までの間、廃棄物を一時的に保管する場合に義務付けられている基準で、代表的なものに以下のようなものがあります。
- 保管期間は、収集・運搬や処理を行うまでのやむを得ない期間のみとする。
- 保管場所の周囲に囲いを設ける。
- 保管場所の見やすい場所に、必要事項を記載した掲示板を設ける。
- 積み上げた産業廃棄物が決められた高さを超えないようにする。
- ネズミやハエ、蚊などの害虫が発生しないようにする。
- 廃棄物の飛散や流出、地下浸透や悪臭の発散が起きないようにする。
委託基準
産業廃棄物の排出事業者が、排出した産業廃棄物の収集・運搬や処理を別の業者に委託する場合に義務付けられている基準で、代表的なものに以下のようなものがあります。
- 委託する業者と書面で契約書を交わす。
- 収集・運搬と処分を別の業者に委託する場合、それぞれ契約書を交わす。
- 契約書は契約終了後5年間保存しておく。
- 産業廃棄物管理票(マニフェスト)を委託する業者に交付し、その処理状況を確認・管理する。
処分基準
産業廃棄物の排出事業者が、産業廃棄物を自ら処分する場合に義務付けられている基準で、代表的なものに以下のようなものがあります。
- 中間処理時に廃棄物が飛び散ったり、漏れ出したりしないようにする。
- 中間処理時の悪臭、騒音、振動等に対して必要な措置を講じる。
- 焼却時には燃焼室ガス温度800℃以上で焼却する。
- 焼却処理には必要な空気量を確保する通風設備を用意する。
- 焼却処理には燃焼室内温度の測定を行う。
- 焼却処理に関して燃焼室温度保持のための助燃装置を設置する。
- 焼却時に煙突先端から火炎・黒煙がでないようにする。
- 焼却時に煙突から焼却灰および未燃物が飛散しないようにする。

お役立ち資料
PDFで詳しく見る
06産業廃棄物問題
最後に、産業廃棄物を取り巻く課題や問題について解説します。
最終処分場不足
産業廃棄物は、リサイクルして別の用途で活用したり、中間処理をして減量化をしたりなど、減らすための取り組みは数多く行われていますが、それでも最終処分として埋立を行わなければならないものも多く、埋立場所である最終処分場の不足が大きな課題となっています。全国にある最終処分場の容量は年々少なくなってきており、各処分場の容量平均はあと10年程とも言われています。
不法投棄
最終処分場の不足と繋がる部分でもありますが、産業廃棄物の処理技術が高まり、また最終処分をする産業廃棄物の数をできるだけ減らさなければならないという動きから、処理費⽤が増加している現状があります。そのため、処理費用を踏み倒す目的で不法投棄が行われてしまうケースも出てきており、1年で1,000件以上の不法投棄が行われているとも言われています。
環境汚染
不法投棄された土地はもちろん、正しく管理された最終処分場においても、地下水の汚染などによる環境汚染が報告されているところもあり、ひどいところでは周囲の人々に健康被害をもたらしてしまっているところもあります。
加えて最終処分場跡地は、不動産取引の際の説明事項にも該当するなど、土地そのものとしての価値も大きく低下させてしまう可能性があります。

お役立ち資料
PDFで詳しく見る
07産業廃棄物のよくある質問
少量でも産業廃棄物として処理しなければなりませんか?
産業廃棄物に量の規定はなく、どれだけ少量であっても産業廃棄物として扱わなければなりません。保管や運搬、最終処分など、すべての処理行程を、産業廃棄物として行っていく必要があります。
ただし「あわせ産廃」という制度があり、例えば少人数の事務所からレジ袋1袋程度のビニールくずが出た場合など、区市町村が認める条件に合致すれば、産業廃棄物を一般廃棄物とあわせて処理することが認められるケースもあります。それ以外にも、例えば事業活動において家庭でも排出されるような洗浄液が排出された場合などは、水濁法や下水道法といった特別法に基づき、そのまま流し台に流しても良いケースがあります。
収集運搬業者Aが受託した産業廃棄物を、他の収集運搬業者Bに再委託することはできますか?
運搬業者から運搬業者への再委託は原則できません。再委託を良しとすることは、廃棄物処理に関する許可制度の趣旨から外れていますし、さらに再委託を重ねることによって責任の所在が不明確になり、不適正処理を引き起こしやすくなってしまうからです。しかし、排出事業者がその旨をあらかじめ書面で承諾しており、加えて施行令で定められている再委託基準を満たしていれば、再委託することができます。再委託が成立した場合、マニフェストは委託業者から再委託業者へと引き渡され、再委託業者から排出事業者へと返送されることになります。
建設工事の現場で、元請業者や下請業者など、複数の業者が存在する場合、排出事業者は誰になりますか?
複数の業者が入るケースも多い建設の現場においては、原則として顧客から直接業務を請けた元請業者が、排出事業者となります。また、その現場で発生した産業廃棄物の収集運搬や処分などの処理を下請業者が行う場合、下請業者は産業廃棄物処理業の許可を持っておく必要があります。例外的に、下請業者が排出事業者と見なされるケースがありますが、「解体や増築以外の建築工事で、請負代金が500万円以下」「1回当たりに運搬される量が1立方メートル以下であることが明白な状態で選別されている」「運搬の途中で保管しない」といった厳しい条件が定められています。
関連するお役立ち資料のダウンロード