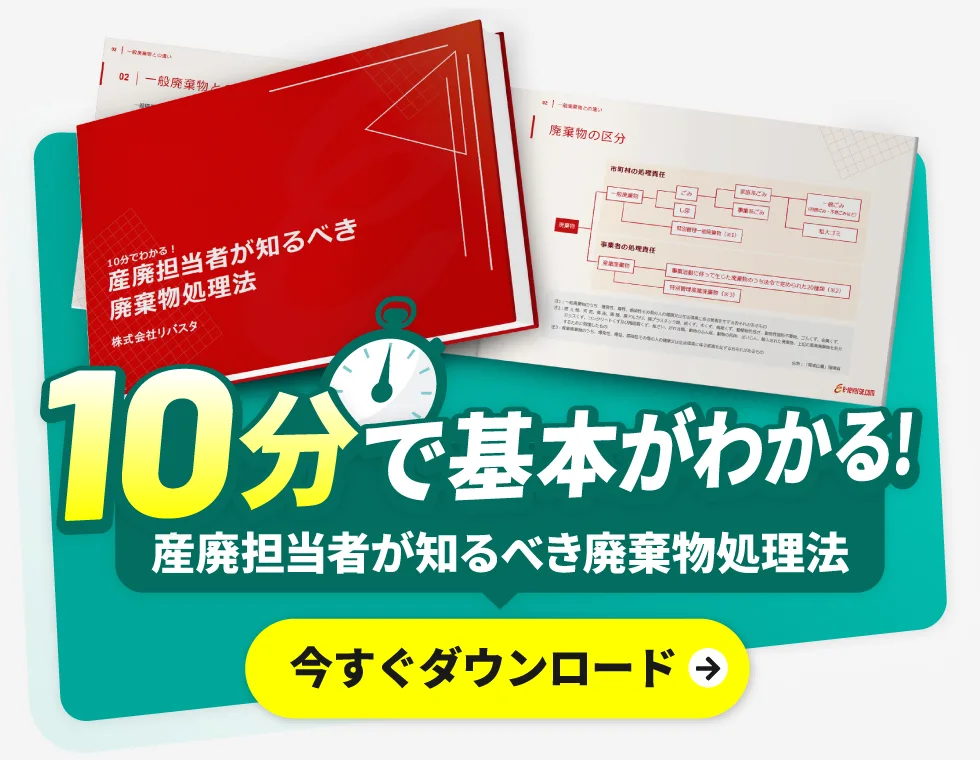建設工事にともない発生するコンクリートやアスファルト、土砂などの建設副産物。これらの適正な処理や再資源化を推進するために、建設副産物実態調査が実施されています。
建設副産物実態調査とは、建設副産物の発生量や再生処理施設の処理状況などを把握するため、一定規模以上の工事や事業者に対して実施される調査です。ただ、具体的に「誰が対象なのか」「どうやって提出するのか」「提出しなかった場合どうなるのか」がわからないという方もいるのではないでしょうか。
本記事では、建設副産物実態調査の概要や対象者、コブリス・プラスを含めた提出方法といった実務担当者が押さえておくべきポイントを解説します。これから調査対応を控えている方は、ぜひ参考にしてください。

お役立ち資料
「産廃担当者が知るべき廃棄物処理法」を1冊にまとめました
新しく産廃担当者となった方向けに、廃棄物処理法を中心に知っておくべきことを簡単に紹介します。
PDFで詳しく見る
目次
0. この記事はこんな読者におすすめ
- 建設副産物実態調査の基本を知りたい方
- 建設副産物実態調査の対象かどうか判断に迷っている方
- 建設副産物実態調査の提出方法を理解したい方

お役立ち資料
PDFで詳しく見る
1.建設副産物実態調査とは
建設副産物実態調査とは、国土交通省が概ね5年ごとに実施する全国規模の調査です。建設工事で発生するコンクリート塊やアスファルト・コンクリート塊、建設汚泥、伐採材などの発生状況や再資源化の実態を把握し、「建設リサイクル推進計画2020」の目標達成状況を確認して今後の施策検討に活用することを目的としています。
なお、令和6年度には、全国で「令和6(2024)年度建設副産物実態調査」が実施されます。この調査は、①利用量・搬出先調査、②再生処理施設の稼働実態調査(施設調査)の二つの調査から構成されています。
1.1.利用量・搬出先調査
利用量・搬出先調査とは、建設工事において使用された資材の量や、そこから発生した建設副産物の搬出先・処理状況などを把握することを目的とした調査です。具体的には、建設資材・再生資材の利用状況、副産物の発生量、搬出先などを詳細に記録します。これにより、全国規模での建設副産物の再資源化率や処理・流通の実態を把握し、建設リサイクルの政策に反映させることが目的です。
1.2.再生処理施設の稼働実態調査(施設調査)
再生処理施設の稼働実態調査(施設調査)とは、建設副産物の処理や再資源化を担う全国の施設に対して、その稼働状況や処理能力、処理実績などを把握することを目的とした調査です。具体的には、建設副産物を取り扱う中間処理施設や最終処分場などを対象に、受け入れ量、再資源化の実施状況、減量化・最終処分の処理状況、製品出荷データなどの詳細な情報を調査します。これにより、全国の処理体制の実態を把握し、建設副産物の適正な循環利用や今後の政策立案に活用されています。
建設副産物実態調査によって得られたデータは「建設リサイクル推進計画2020」の目標達成状況の把握や「建設リサイクル法」、「建設リサイクル推進計画」などの諸施策に関する検討、評価などに役立てられています。建設副産物実態調査は、建設業界における環境対策や循環型社会の実現に向けて、重要な役割を担っているといえます。

お役立ち資料
PDFで詳しく見る
2.建設副産物実態調査の対象者
令和6(2024)年度建設副産物実態調査を構成する利用量・搬出先調査は、令和6年度(2024年4月1日から2025年3月31日までの間)に完成した建設工事を対象に実施されますが、再生処理施設の稼働実態調査(施設調査)は、令和6年度における建設副産物の中間処理施設や最終処分場など、再生処理施設の稼働状況や立地状況、処理能力などを把握することを目的としています。したがって、両調査では対象が異なります。ここでは、利用量・搬出先調査の対象者と対象工事、再生処理施設の稼働実態調査(施設調査)の対象者を解説します。
2.1.利用量・搬出先調査の対象者
利用量・搬出先調査では、対象となる建設工事を完了した元請業者が、調査票の記入および提出をおこなう責任を負います。令和6(2024)年度建設副産物実態調査における対象工事は以下の通りです。これらの条件に該当する元請業者は、調査票の提出が求められます。
| 公共・民間公益工事 (電力、ガス、電気通信、鉄道の各社が発注する工事) |
令和6年度に完成した請負金額100万円以上の工事 |
|---|---|
| 民間工事 |
|
なお、上の表の右にある「民間工事の資源有効利用促進法に定められている一定規模以上の工事」の定義は以下の通りです。
| 再生資源利用計画書(実施書) | 再生資源利用促進計画(実施書) |
|---|---|
次のいずれか1つでも満たす建設資材を搬入する建設工事
|
次のいずれか1つでも満たす指定副産物を搬出する建設工事
|
2.2.再生処理施設の稼働実態調査(施設調査)の対象者
再生処理施設の稼働実態調査(施設調査)は、建設副産物を取り扱う中間処理施設、最終処分場などを対象に実施されます。調査対象となった施設には、各地方連絡協議会事務局から通知が届き、定められた方法に従って調査票の記入・提出を行う仕組みです。

お役立ち資料
PDFで詳しく見る
3.建設副産物実態調査の提出方法
利用量・搬出先調査と再生処理施設の稼働実態調査(施設調査)では、提出方法が異なります。ここでは、それぞれの調査の提出方法を見ていきましょう。
3.1.利用量・搬出先調査の提出方法
利用量・搬出先調査の調査対象となった元請業者は、3種類の方法のいずれかで報告を行う必要があります。
1つ目は、コブリス・プラスを利用する方法です。コブリス・プラスは、建設リサイクル法により義務づけられている書類の作成や、「利用量・搬出先調査」の作成をおこなうことができるため、公共工事及び民間公益工事において、使用が推奨されています。コブリス・プラスで作成したデータはオンラインシステムに登録されるため、別途調査票の提出は不要です。
2つ目は、国土交通省のホームページより配布されている「建設リサイクル報告様式」を用いて提出する方法です。Excel形式の報告書を作成し、各発注機関、または各地方連絡協議会の窓口へ電子メールなどで提出します。
3つ目は、国土交通省のホームページで配布されている「建設副産物実態調査シート(Excel)」(通称「実態調査入力シート」)に記入し、同様に各発注機関、または各地方連絡協議会の窓口へ電子メールなどで提出する方法です。報告様式と同じくExcelファイルで作成するため、使いやすい方を選んで提出できます。
なお、「建設リサイクル報告様式」または「実態調査入力シート」で作成したExcelファイルは、提出前に専用の「利用量・搬出先調査エラーチェックツール」を用いてエラーの確認と修正を行うことが推奨されています。
3.2.再生処理施設の稼働実態調査(施設調査)の提出方法
再生処理施設の稼働実態調査(施設調査)では、指定の調査票に必要事項を入力し、所在地の都道府県を管轄する連絡協議会に電子メールなどで提出します。調査票はExcel形式で国土交通省のホームページから入手可能です。施設調査票の記入例が参考資料として提供されているため、初めて提出する場合でも円滑に対応できるよう配慮されています。
また、入力ミスや記載漏れを防止するために、「施設調査エラーチェックツール」も用意されています。作成した調査票を提出する前にこのツールで確認することで、後日の修正依頼や差し戻しのリスクを軽減することができます。

お役立ち資料
PDFで詳しく見る
4.建設副産物実態調査を提出しなかった場合の罰則
建設副産物実態調査は国のリサイクル施策や環境政策に活用する目的で実施される重要な調査ですが、未提出に対して罰金や行政処分といった直接的な罰則は設けられていません。
ただし、「罰則がない=提出しなくてもよい」と解釈するのは適切ではありません。調査は国土交通省の要請のもとで実施され、各自治体や関係機関を通じて積極的な協力が求められています。
提出を怠った場合、直ちに法的な罰則が科されることはないものの、行政や発注機関との信頼関係に影響を及ぼし、将来的な入札や契約に間接的な悪影響を及ぼす可能性があります。また、調査協力率の低下が続いた場合には、制度の強化や義務化が検討される可能性もあります。
以上の理由から、建設副産物実態調査の対象となった際は、利用量・搬出先調査と再生処理施設の稼働実態調査(施設調査)の意義を理解したうえで、期日内に正確な内容で提出することが求められるでしょう。

お役立ち資料
PDFで詳しく見る
関連するお役立ち資料のダウンロード