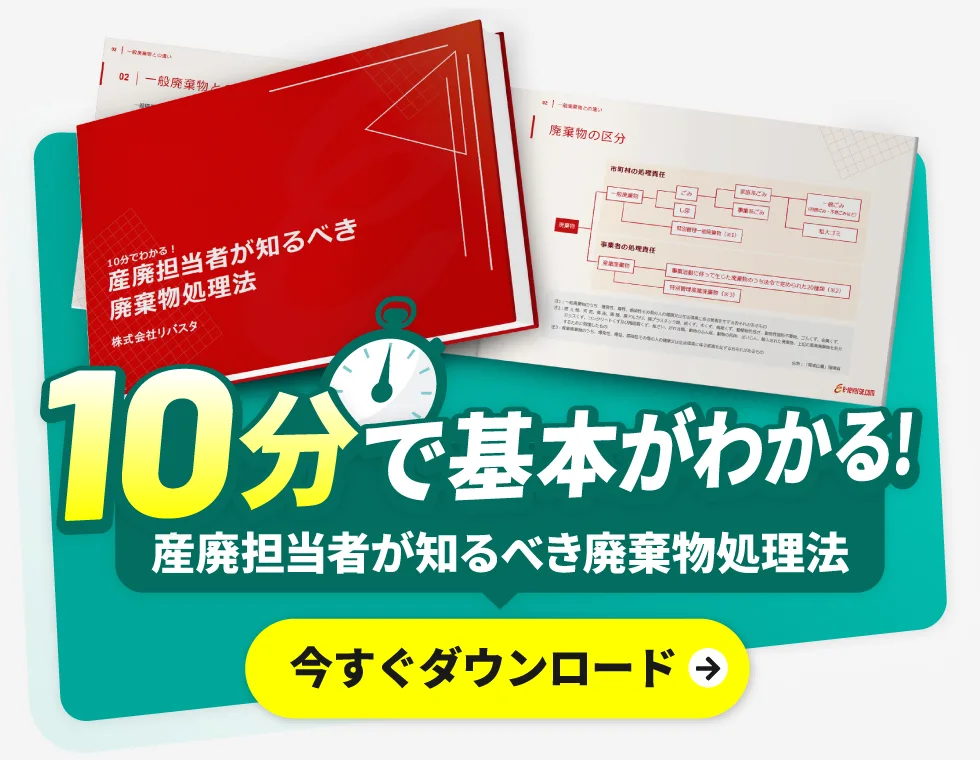「ストックヤード運営事業者登録制度」は、建設発生土の適正な管理と利用を促進するための制度ですが、まだ詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。登録すれば、元請業者からの信頼を得やすくなり、メリットも得られます。ここではストックヤード運営事業者登録制度について概要やメリット、業務内容、登録方法などについて解説します。

お役立ち資料
「産廃担当者が知るべき廃棄物処理法」を1冊にまとめました
新しく産廃担当者となった方向けに、廃棄物処理法を中心に知っておくべきことを簡単に紹介します。
PDFで詳しく見る
目次
0.この記事はこんな読者におすすめ
- ストックヤード運営事業者登録制度の詳しい内容を知りたい方
- ストックヤード運営事業者登録制度のメリットを知りたい方
- 今後ストックヤード運営事業者登録制度の登録の流れや手続きを知りたい方

お役立ち資料
PDFで詳しく見る
1.ストックヤード運営事業者登録制度とは
ストックヤード運営事業者登録制度は、建設工事で発生する土砂(建設発生土)の適正な管理と利用を促進するために、国土交通省が創設した登録制度です。対象は、建設発生土を一時的に保管する場所である「ストックヤード」を運営する事業者になります。登録された事業者は、土砂の搬入から搬出までの履歴を管理し、その情報を国に報告しなければなりません。
ストックヤード運営事業者登録制度は、建設発生土がどこのストックヤードに運ばれ、最終的にどのように使用、または処分されるのかを明確にし、不適切な盛土の防止を目指しています。登録されたストックヤード運営事業者は、土砂の適正な流れを担保する役割を担うことになるのです。単に土砂の管理を厳格化するだけでなく、建設発生土のリサイクルを促進し、持続可能な社会の実現にも貢献できるでしょう。

お役立ち資料
PDFで詳しく見る
2.ストックヤード運営事業者登録制度の創設の背景
ストックヤード運営事業者登録制度が創設された背景には、2021年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害の影響が大きくあります。この災害は、盛土によって形成された不安定な造成地が崩落し、甚大な被害をもたらしました。不適切な盛土や土砂管理が大規模災害の原因となり得ることを、社会に強く認識させる契機となりました。これまで、土砂の管理は、必ずしも厳格ではなく、発生した土砂の搬出先や利用実態を把握することが困難な状況にありました。そのため、不法投棄や無許可の盛土が後を絶たず、全国各地で土砂災害のリスクを高める要因となっていました。
この状況を受け、2023年に5月26日に施行されたのが、「旧宅地造成等規制法」を改正し、より広範な区域を対象とした「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)です。
盛土によって災害発生のリスクがある区域を「規制区域」として指定し、区域内での盛土や切土について都道府県知事等の許可を義務付けるなど、安全確保のための規制を大幅に強化しました。
ストックヤード運営事業者登録制度は、盛土規制法の施行と連動して導入された制度です。盛土規制法が「どこに盛土をしてはいけないか、実施するならどういう許可が必要か」を定める法律であるのに対し、ストックヤード運営事業者登録制度は「土砂がどのように処理させるかを明確にして適正な流通を促す」のが目的としています。発生した土砂が許可のない場所へ不法に運ばれるのを防ぎ、適正な利用先へと確実に誘導するための重要な仕組みとして位置づけられています。

お役立ち資料
PDFで詳しく見る
3.元請業者がストックヤードを利用するメリット
2023年5月26日から施行された盛土規制法は、元請業者にとっては大きな負担となるのは避けられません。しかし、国土交通大臣の登録を受けたストックヤードに建設発生土を搬出することで、以下のようなメリットがあります。元請業者がストックヤードを利用するメリットを解説します。
業務負担の大幅な軽減
これまで、土砂の最終搬出先が多岐にわたる場合、全てを把握し、確認するのは膨大な時間と労力を要する作業でした。登録ストックヤードを利用することで、確認作業から解放され、本来の建設業務に専念できるようになります。
コンプライアンスリスクの軽減
不適切な盛土や不法投棄に土砂が利用された場合、元請業者もその責任を問われる可能性があります。しかし、登録ストックヤードは、国の基準を満たし、適正な管理が義務付けられているため、コンプライアンス上のリスクを大幅に軽減できます。
取引先選択肢の明確化
登録された事業者の一覧は国土交通省のウェブサイトで閲覧可能です。元請業者は、信頼性の高い搬出先を優先的に選ぶことが可能になります。

お役立ち資料
PDFで詳しく見る
4.登録ストックヤード事業者の業務内容
国土交通大臣の登録を受けたストックヤード運営事業者は、建設発生土の適正な管理のために、重要な業務を担います。登録ストックヤード事業者の適切な業務遂行が、制度の信頼性を担保し、不適切な土砂の流通を防ぐ上で不可欠です。
主な業務内容は以下の通りです。
搬入時
ストックヤードに建設発生土が搬入される際、登録事業者は以下の事項を厳格に確認し、記録を作成する必要があります。
- 搬入元ごとの土砂搬入量の管理、記録・保存
どの工事現場から発生した土砂であるか(工事名称、所在地、元請業者など)、搬入量はどのくらいかなどを確認します。また、土砂搬入量管理の記録を5年間保存しなければなりません。 - 搬入元ごとに「土砂受領書」の交付・保存
搬入元に対して、土砂を受領したことを示す書面(受領書)を交付します。記載内容を詳細に記録し、原則として搬入日から5年間保管します。
搬出前
ストックヤードから土砂が搬出される前には搬出先の適正確認をし、「適正確認記録」を作成・保存しなければなりません。土砂の搬出先が盛土規制法、都道府県の定める土砂条例の許可等を得ているかの事前確認が必要です。
「ストックヤードから搬出する土砂の搬出先の適正確認について」のフローを元に確認し、不適正と判定された場合は搬出先として認められません。盛土規制法の区域指定がおこなわれているかどうか、都道府県等の土砂条例が指定されているかどうかで確認方法が変わるので注意が必要になります。
搬出時
ストックヤードの搬出時は、土砂運搬者へ搬出先名称、所在地、搬出先適正確認結果を運搬者に通知する必要があります。
搬出後
土砂がストックヤードを離れた後も事業者の責任は継続し、以下の業務を実施しなければなりません。
- 搬出先ごとに土砂搬出量の管理、記録をし、5年間保存
- 搬出先ごとに「土砂受領書」の交付を求め、交付された受領書を5年間保存
- 「適正確認記録」と交付された「土砂受領書」の記載内容が一致していることを確認
- 一次搬出先からさらに他の搬出先へ出された場合、(二次、三次搬出先等の)最終搬出先までの記録を作成・保存し、記録の写しを5年間保存

お役立ち資料
PDFで詳しく見る
5.登録の流れと必要な手続き
ストックヤード運営事業者登録制度は、外部から搬出された土砂を一時的に堆積する場所を管理する者であれば申請可能です。申請するストックヤードは自社所有でなくても問題ありませんが、申請者が管理していることが条件になります。登録の流れは以下の通りです。
申請
主たる事務所(本社等)の所在地を管轄する地方整備局等へ電子メールなどで申請します。以下の書類の準備が必要で、国土交通省のウェブサイトからダウンロードが可能です。
- 申請書兼変更届出書等
- 誓約書
- 身分証明書
- 役員の住所等に関する調書
- 登記事項証明及び定款
- 法定代理人の登記事項照明
- 許可証などの写し
- 土砂搬入搬出管理票
登録
登録が完了後、地方整備局等から登録通知と登録済ファイルが返送されます。有効期間は登録日から5年間です。
業務
登録ストックヤード運営事業者として適切に業務を実施します
報告
事業年度ごとに国(地方事務局等)へ搬入搬出管理年報の報告が必要です。各事業年度の終了後3ヵ月以内に報告をしなければなりません。
更新
5年ごとの更新が必要です。申請時期は有効期間満了日の180日前から42日前になります。

お役立ち資料
PDFで詳しく見る
関連するお役立ち資料のダウンロード