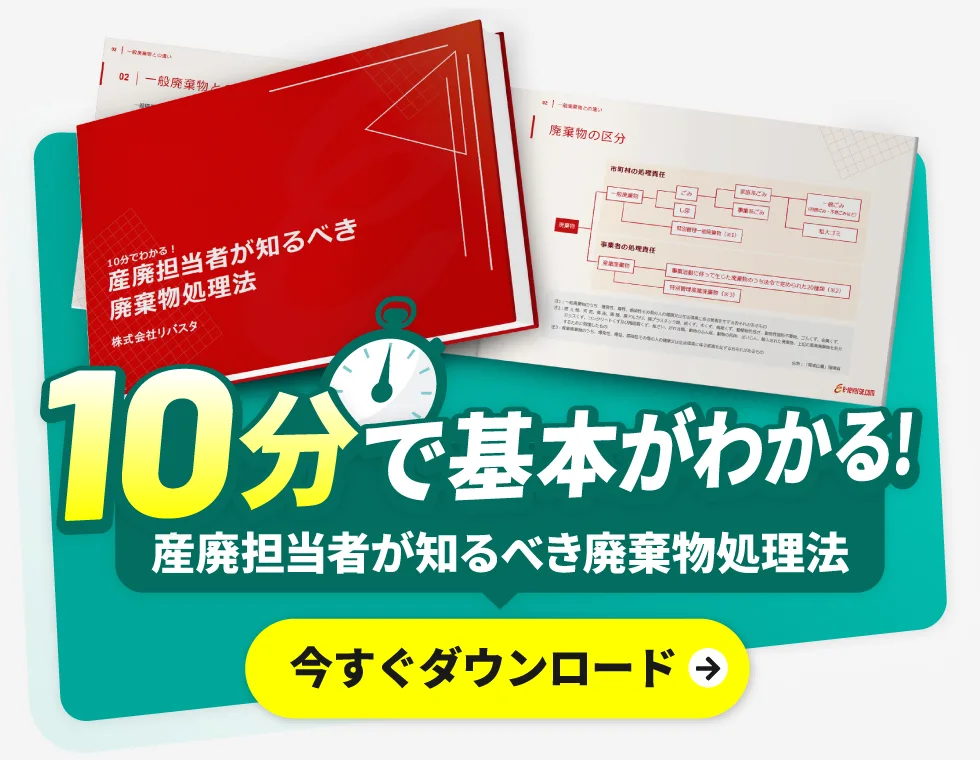有害物質による土壌汚染の原因は、特定有害物質を扱う工場の操業や地下水汚染等の人為的な要因に加え、自然由来の汚染が原因となる場合もあります。土壌汚染は、私たちの健康や暮らしを脅かすだけでなく、土地の資産価値にも深刻な影響を及ぼすおそれがあります。このようなリスクを防ぐために制定されているのが「土壌汚染対策法」です。土壌汚染対策法の内容を理解することは、土地利用や事業活動を行ううえでも重要です。
本記事では、土壌汚染対策法の概要や制定の背景、土壌汚染の主な原因と健康リスク、そして土壌汚染の調査・区域指定・対策といった法律の仕組みまで、詳しく解説します。

お役立ち資料
「産廃担当者が知るべき廃棄物処理法」を1冊にまとめました
新しく産廃担当者となった方向けに、廃棄物処理法を中心に知っておくべきことを簡単に紹介します。
PDFで詳しく見る
0.この記事はこんな読者におすすめ
- 土壌汚染対策法の基本を知りたい方
- 土壌汚染の原因や健康リスクを知りたい方
- 土壌汚染対策法に業務で携わる方

お役立ち資料
PDFで詳しく見る
1.土壌汚染対策法とは
土壌汚染対策法は、特定有害物質に指定されている重金属や揮発性有機化合物などによる土壌汚染の問題が顕在化し、健康影響への不安や対策措置を求める社会的要請が強まったことを背景に制定された法律です。土壌の特定有害物質による汚染状況を把握し、その汚染によって健康被害が生じるのを防ぐための措置を定め、土地の利用者や事業者が安心して土地を利用できる環境を整備し、国民の健康を保護することを目的としています。
この法律は、平成14年(2002年)5月29日に公布され、平成15年(2003年)2月15日に施行されました。その後も、適切なリスク管理を推進する目的で改正が継続的に行われています。
土壌汚染対策法では、土壌汚染を引き起こすおそれのある事業所や、大規模な土地での工事などに土壌調査や届出を義務づけています。汚染が確認された土地は、「指定区域」として登録・管理し、将来の土地利用でも適切な対応が取られる仕組みを設けています。

お役立ち資料
PDFで詳しく見る
2.土壌汚染の原因
土壌汚染とは、私たちが安全に生活する上で不可欠な土壌が、有害物質の浸透・蓄積によって汚染された状態を指します。土壌汚染の原因は多岐にわたりますが、主な原因としては、以下の3点が挙げられます。
- 工場・事業場での有害物質の直接漏出
工場や研究施設の操業過程で、重金属(カドミウム、ヒ素、六価クロムなど)や揮発性有機化合物(四塩化炭素、トリクロロエチレンなど)が設備の故障や不適切な取り扱いにより直接地下に漏れ出すことで土壌汚染が発生します。 - 産業廃棄物の不適切な埋設処理
有害物質を含む固形廃棄物が適切に処理されることなく土壌に埋設されることによって生じる土壌汚染です。この場合、廃棄物に含まれる有害物質が雨水と接触することで溶出し、周辺の土壌や地下水に拡散するという、液体の直接漏出とは異なるメカニズムで汚染が進行します。 - 自然由来の要因
土壌汚染には、人為的要因によるものだけでなく、地層中に自然由来で存在する砒素、鉛、ふっ素などにより汚染されているケースもあります。

お役立ち資料
PDFで詳しく見る
3.土壌汚染による健康リスク
土壌汚染は、私たちの健康にも深刻な影響を及ぼすおそれがあります。土壌汚染対策法 では、土壌汚染による健康リスクを「直接摂取するリスク」と「地下水など経由の摂取リスク」の2つに分類しています。
- 直接摂取するリスク
汚染された土地に直接触れたり、そこに生えた農作物を食べたりすることで、土壌に含まれる有害物質を口や肌などから直接摂取し健康被害が生じるリスクです。例えば、子どもが砂場遊びをしているときに手についた土壌を口にする、風で飛び散った土壌が直接口に入ってしまう場合などが挙げられます。このリスクに対しては、特定有害物質のうち9物質に土壌含有量基準が設定されています。 - 地下水等経由の摂取リスク
土壌中の有害物質が地下水に溶け出し、その地下水を口にすることによるリスクです。例えば、汚染された土地の周辺に、地下水を飲用するための井戸がある場合、地下水を飲用水として使用することで、有害物質が体内に取り込まれるリスクがあります。このリスクには全ての特定有害物質(26物質)に対して土壌溶出量基準が設定されています。

お役立ち資料
PDFで詳しく見る
4.土壌汚染対策法のしくみ
土壌汚染対策法には、大きく分けて「調査」「区域指定」「対策・管理」の流れがあります。それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
汚染の調査
土壌汚染の状況を把握するための調査は、原則として環境大臣または都道府県知事が指定した専門の調査機関(指定調査機関)が、以下のいずれかのタイミングで実施します。
- 有害物質使用特定施設の使用廃止のとき(法第3条)
有害物質を扱う工場等の特定施設が廃止された場合、原則として土地の所有者等に土壌汚染状況調査を実施する義務が生じます。ただし操業を継続する場合などは、一時的に調査の免除を受けることが可能です(法第3条第1項ただし書き)。また、この免除を受けている土地で900㎡以上の土地の形質変更を行うときは、原則として届出を行い、都道府県知事等の命令により調査を行う必要があります(法第3条7項・8項)。 - 一定規模以上の土地の形質変更の届出の際(法第4条)
土地の形質変更を行う場合で、都道府県知事等が土壌汚染のおそれがあると判断したときに調査が必要になります。規模の目安としては、「3,000㎡以上の土地の形質変更」や「有害物質使用特定施設がある土地で900㎡以上の形質変更」の場合に届出が必要です。この届出に先立ち、土地所有者などの全員の同意を得て自主的に調査を行い、その結果を併せて提出することも可能です(法第4条第2項)。 - 土壌汚染により健康被害のおそれがあるとき(法第5条)
土壌汚染により人の健康被害を生ずるおそれがあると都道府県知事等が認めたときに、土地の所有者等に調査を命じられる場合があります。
土壌汚染の区域指定
土壌汚染状況調査の結果、基準を超える汚染が確認された場合は、土地は健康被害のおそれの有無に応じて次のいずれかの区域として指定されます。区域指定の情報は公開され、都道府県が作成・管理する台帳で公開されます。
- 形質変更時要届出区域(法第11条)
汚染は確認されたものの、土壌汚染の摂取経路がなく、人の健康被害を直接引き起こすおそれが低いため、汚染除去等の措置は不要な区域です。摂取経路が遮断されている区域も含まれます。土地の形質変更を行う際には、都道府県知事等に事前届出が必要です。基準に適合しない土壌が区域内に存在しなくなると、形質変更時要届出区域の指定が解除されます。 - 要措置区域(法第6条)
土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生じるおそれがあるため、汚染の除去や拡散防止等の措置が必要な区域です。土地所有者は、都道府県知事の指示に係る汚染除去計画を作成して実施し報告する義務があります(第7条)。原則として土地の形質の変更が禁止されます(第9条)。汚染の除去が実施され、摂取経路が遮断される場合には、要措置区域の指定が解除され、形質変更時要届出区域に指定されます。
汚染された土地の対策と管理
土壌汚染対策法では、特定有害物質による土壌汚染の状況を把握し、その汚染によって人の健康に被害が生じるのを防ぐための措置を定めています。
要措置区域の土地の所有者などは、都道府県知事等に提出して確認を受けた汚染除去等計画書に基づいて、汚染の除去等の措置を行わなければいけません。都道府県知事等は講ずべき汚染の除去等の「指示措置」を提示し、汚染除去等計画の作成を指示します。土地所有者等は「指示措置」及びこれと同等以上の効果を有すると認められる汚染の除去等の措置のうちから、措置を選択することができます。土地所有者等は、汚染除去等計画に記載された実施措置が完了した際、都道府県知事等に措置の完了報告をしなければなりません。
地下水等経由の摂取リスクのある土地
≪指示措置≫
- 地下水質の測定
地下水汚染が生じていないか、また、地下水汚染が生じているが目標土壌溶出量及び目標地下水濃度に適合している土地の場合、目標の土壌溶出量や地下水濃度を超えていないことを確認するため、定期的に地下水の水質の測定を行います。 - 封じ込め
汚染土壌を封じ込めて地下水などによる汚染の拡散を防ぐための措置です。原位置封じ込めや遮水工封じ込め、遮断工封じ込めなどがあります。
≪同等以上の効果ありと認められる措置の例≫
- 不溶化処理
- 遮断工封じ込め
- 汚染土壌の除去
- 地下水汚染の拡大の防止 など
直接摂取リスクのある土地
≪指示措置≫
- 盛土
土壌含有量基準に適合しない場合に、地表面を砂利などで覆い、加えて厚さ50cm以上の汚染されていない土壌により覆うことで、直接摂取経路を遮断する措置です。 - 土壌汚染の除去
汚染された土壌を浄化、あるいは除去する措置です。掘削・除去や原位置浄化等があります。指示措置が土壌汚染の除去とされるのは、土地の用途からみて限定的な場合になります。 - 土壌入換え
土壌含有量基準に適合しない場合、地表から深さ50cmまでの汚染土壌を掘削除去し、汚染されていない土壌で埋め戻して直接摂取の経路を遮断する措置です。
≪同等以上の効果ありと認められる措置≫
- 土壌入換え
- 舗装
- 立入禁止
- 土壌汚染の除去など
対策完了後も、再拡大の有無を確認するため、定期的なモニタリング調査の実施が義務付けられています。一方、形質変更時要届出区域では、土地の掘削や造成を行う際には届出が必須となり、必要に応じて追加調査や対策を講じることで、リスク管理が継続されます。

お役立ち資料
PDFで詳しく見る
関連するお役立ち資料のダウンロード