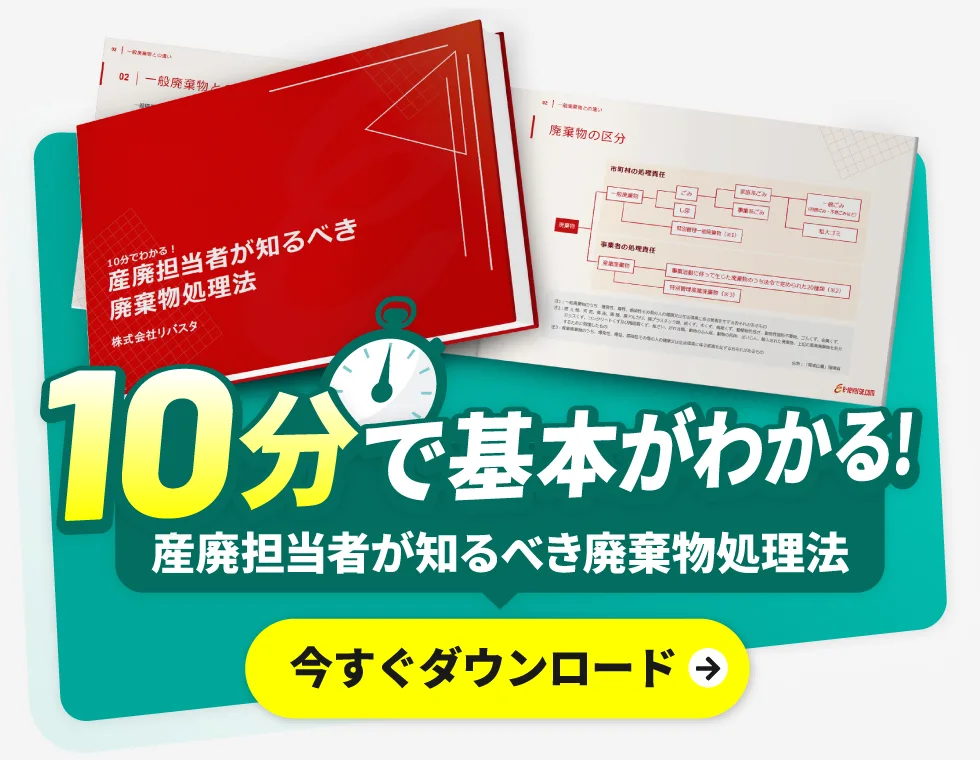2021年に発生した熱海の大規模土砂災害を契機に、旧「宅地造成等規制法(宅造法)」が抜本的に改正され、2023年5月26日に「盛土規制法」として施行されました。ここでは、盛土規制法の対象となる「盛土等」の具体的な内容や、旧宅造法も含めて盛土規制法が制定された背景を紹介し、旧宅造法からの変更点、規制の対象となる「盛土等」の行為・規模について解説します。また、盛土等を実施する際の手順と手続き、違反した場合の罰則規定など、土地造成を担う事業者の方にとって重要な情報をお届けします。

お役立ち資料
「産廃担当者が知るべき廃棄物処理法」を1冊にまとめました
新しく産廃担当者となった方向けに、廃棄物処理法を中心に知っておくべきことを簡単に紹介します。
PDFで詳しく見る
目次
0.この記事はこんな読者におすすめ
- 盛土規制法について詳しく知りたい方
- 旧宅地造成等規制法との違いを知りたい方
- 宅地造成や盛土等を実施する事業者、土地所有者の方

お役立ち資料
PDFで詳しく見る
1.盛土規制法とは
「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)は、盛土や切土の崩落による災害から国民の生命および財産を守ることを目的として制定されました。盛土規制法は、1962年に施行された「宅地造成等規制法」を抜本的に改正したものであり、対象を宅地に限定せず、危険と判断される盛土等については土地の用途を問わず規制の対象とされます。
<盛土規制法の概要>
- 規制区域の指定
盛土や切土の崩落、土砂の流出などにより、人家への被害が想定される区域は、都道府県知事等により規制区域に指定されます。規制区域内では、盛土や切土に加えて、土砂の廃棄や一時的な土石置き場も対象となり、宅地や農地、森林など土地の用途にかかわらず、全国一律の基準で規制を受けます。 - 安全な盛土等の造成
規制区域内で盛土等を実施する場合は、都道府県知事、指定都市および中核市の市長から許可を受ける必要があります。許可申請にあたっては、国が定めた安全対策基準への適合、工事主の資力と信用、施工者の能力などが求められます。また、土地の所有者全員の同意と、周辺住民に対する説明会等による事前周知が必要です。 - 盛土等の保全責務
規制区域内の盛土等は常に安全な状態を維持しなければなりません。この責務は、「土地の所有者」「管理者」「占有者」が負う必要があり、土地が譲渡された場合には、譲渡を受けた所有者等に責務が発生します。また、過去の所有者などでも、災害が起こる原因をつくったとみなされる場合は、その者に是正措置等の命令が下されることもあります。 - 罰則
無許可行為、虚偽の申請、命令違反などの違反行為には、拘禁刑や罰金などの厳しい処罰が科せられます。

お役立ち資料
PDFで詳しく見る
2.盛土規制法の背景
盛土規制法の旧法にあたる「宅地造成等規制法(宅造法)」は、1961年に日本全国を襲った豪雨の被害を教訓として制定されました。この年は6月下旬から梅雨前線が本州の南側にとどまり、そこに接近した台風の影響と相まって、日本全国に大雨をもたらしました。
その結果、全国各地にがけ崩れや土砂の流出などの被害をもたらしましたが、特に宅地造成された土地や造成中の宅地で、多数の犠牲者と甚大な損害が発生しました。これを契機として、翌1962年に「宅地造成等規制法」が施行されました。これ以降、宅地造成工事は規制対象とされ、都道府県知事の許可制となりました。
それから約60年後の2021年7月、静岡県熱海市で発生した大規模な土砂災害を受けて「宅地造成等規制法」は抜本的に見直され、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称・盛土規制法)に改正されました。熱海で発生した土石流も三六災害と同様に梅雨前線による大雨が原因でしたが、被害を甚大にしたのは、土石流が起きた逢初川の源流付近につくられた盛土が崩落したためです。
この盛土は届け出を大きく超える規模で造成されており、所有者に対しては対策をとるよう再三にわたり行政指導がなされていました。しかし、盛土の所有者はこれを放置し、1ヵ所で起きた土砂災害としては過去最大級の被害を引き起こす原因となりました。この人災ともいえる大規模災害の翌年、旧法が改正され、「盛土規制法」が制定され、2023年5月26日に施行されました。

お役立ち資料
PDFで詳しく見る
3.従来の宅地造成等規制法からの変更点
従来の「宅地造成等規制法」では、造成済みまたは造成中の宅地に限って規制が行われていたのに対し、改正された「盛土規制法」では宅地、森林、農地など土地の用途を問わず、盛土や切土が規制対象となります。この点が旧宅造法からの大きな変更点です。
また、旧宅造法では土捨てや一時的な土石置き場なども規制の対象外でした。こうした法規制のスキマをなくすために、旧法を抜本的に見直した「宅地造成及び特定盛土等規制法」に改め、都道府県による違いのない全国一律の基準で規制がされるようになりました。

お役立ち資料
PDFで詳しく見る
4.盛土規制法の対象となる行為とは?
盛土規制法の「盛土等」には盛土や切土、土捨てをおこなう場所や一時的な土石置き場・ストックヤードなどが含まれます。盛土とは、文字通り土を盛り上げて平らな土地にする行為であり、低い地盤を底上げした土地や斜面の一部を平らにした土地、あるいはその工事を指します。一方、切土は盛土とは逆に、高い地盤を切り取ったり、斜面を切り下げて平坦にした土地、あるいはその工事を指します。
一般的に切土のほうが盛土よりも地盤が硬く、高い崖をもうけることが可能で、掘割のように連続した切土をおこない道路や水路、鉄道などに利用することができます。なお、盛土規制法では対象区域を二つに区分して指定しており、規制の対象となる行為と規模がそれぞれ定められています。
- 宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われた場合に人家などへ危害を及ぼすおそれがあるエリア - 特定盛土等規制区域
市街地や集落などから離れた場所であっても、地形等の条件から、盛土等がおこなわれれば人家等に危害を及ぼすおそれがあるエリア
<盛土規制法の対象となる行為・規模>
| 宅地造成等工事規制区域 (許可が必要な行為) |
土地の形質の変更 (盛土・切土) |
|
|---|---|---|
| 一時的な土石の堆積 |
|
| 特定盛土等規制区域 (許可が必要な行為) |
土地の形質の変更 (盛土・切土) |
|
|---|---|---|
| 一時的な土石の堆積 |
|
| 特定盛土等規制区域 (届出が必要な行為) |
土地の形質の変更 (盛土・切土) |
|
|---|---|---|
| 一時的な土石の堆積 |
|

お役立ち資料
PDFで詳しく見る
5.盛土をおこなう際の手続き
盛土や切土を実施する際には、以下の手順に従って手続きを行う必要があります。
- 許可申請前
- 土地所有者全員の同意を得る
- 説明会の開催などによる、周辺住民への事前周知
- 工事許可申請・許可
- 以下の許可基準を満たすこと
- 定められた安全対策基準に適合すること
- 工事主が許可に必要な資力・信用を有すること
- 工事施工者が必要とされる能力を有すること
- 土地所有者全員の同意を得ていること
※工事主とは、盛土等を請け負う工事や運搬作業などの発注者、または自ら盛土等の 工事や残土処分などを行う事業者を指します。
- 都道府県知事等の許可
- 以下の許可基準を満たすこと
- 工事着手
- 現場に許可を受けていることを示す標識を掲出する
- 3ヵ月ごとに定期報告を行う
- 工事完了後では確認が困難な工程の中間検査を実施する
- 工事完了時に現地検査を受ける

お役立ち資料
PDFで詳しく見る
6.盛土規制法における罰則規定
盛土規制法では、工事完了後も盛土や切土を安全な状態に維持する責務を土地の所有者等に課しており、違反行為には厳しい罰則が科せられます。罰則の対象は土地の所有者にとどまらず、実際に造成をおこなった事業者や過去の土地所有者など、災害の原因をつくった「原因行為者」も含まれます。
<主な罰則規定>
- 無許可で宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積工事を行った場合
- 工事計画を無許可で大幅に変更した場合
- 不正な手段で許可を受けた場合
- 盛土等の安全維持など是正措置命令を受け、この命令に従わない場合
上記のいずれかに該当する場合、3年以下の拘禁刑・1000万円以下の罰金に処せられます。また、法人に対しては最大3億円の罰金が科せられる場合もあります。

お役立ち資料
PDFで詳しく見る
関連するお役立ち資料のダウンロード