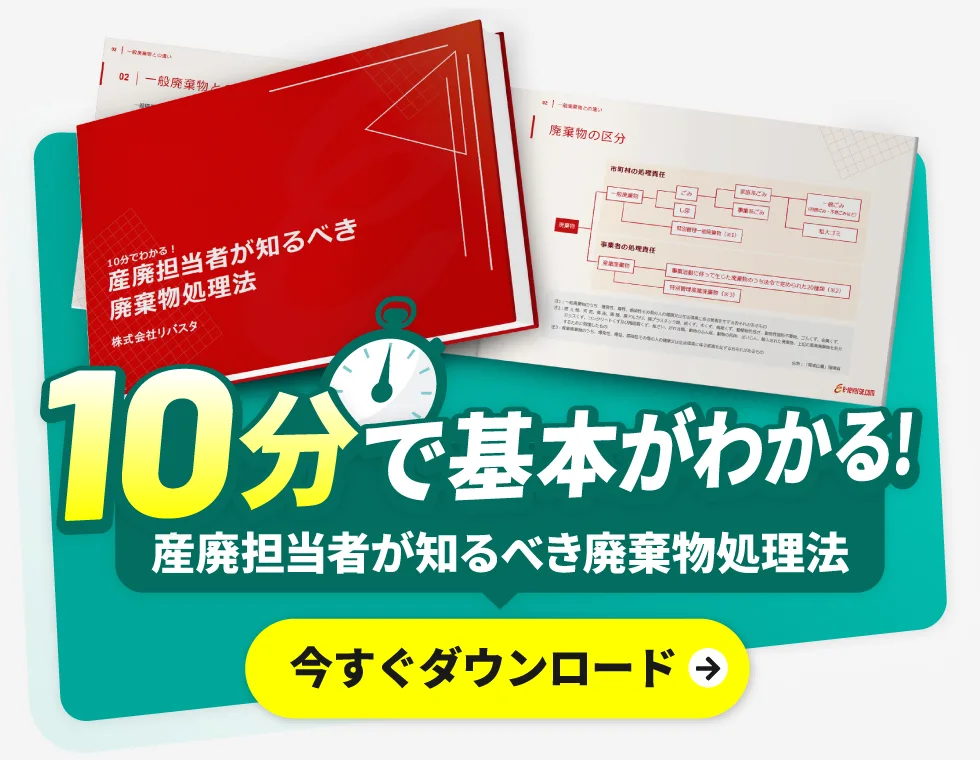企業の環境対応やサステナビリティが重視される中、資源の効率的な利用を促す「資源有効利用促進法」への注目が高まっています。この法律は、3R(リデュース・リユース・リサイクル)を通じて廃棄物を減らし、循環型社会の構築を目指すものです。企業には製品設計から回収・再資源化に至るまで、幅広い責任が課せられています。
この記事では資源有効利用促進法の概要から改正のポイント、建設工事における責任、さらに企業が取り組むべき3Rのルールまでをわかりやすく解説します。

お役立ち資料
「産廃担当者が知るべき廃棄物処理法」を1冊にまとめました
新しく産廃担当者となった方向けに、廃棄物処理法を中心に知っておくべきことを簡単に紹介します。
PDFで詳しく見る
目次
0. この記事はこんな読者におすすめ
- 資源有効利用促進法の基本から知りたい方
- 法改正や企業に求められる対応内容を押さえたい方
- 建設業など関連業種に携わる方

お役立ち資料
PDFで詳しく見る
1. 資源有効利用促進法とは
資源有効利用促進法は、循環型社会の実現に向けて制定された法律です。ここでは、法律の基本情報や制定の背景、制度の目的と仕組みについて解説します。
法律の基本情報と背景
資源有効利用促進法は、正式名称を「資源の有効な利用の促進に関する法律」といい、2001年(平成13年)4月に施行されました。この法律は、循環型社会形成推進基本法の理念を踏まえ、ゴミの大量発生や最終処分場のひっ迫といった廃棄物問題に対応するために制定されました。廃棄物のリデュース(抑制)・リユース(再使用)・リサイクル(再資源化)の3Rを推進するための法律です。
制度の目的と仕組み
制度の目的は、3Rを通じた廃棄物の削減と資源の有効利用を促進し、循環型経済システムの構築を支えることです。
政令で10業種・69品目を指定し、それらの製造業者や事業者に対して省令で以下のような取り組みを義務付けています。
- 製品の設計・製造段階での省資源化や長寿命化
- 識別表示による分別回収の促進
- 自主回収・リサイクル体制の整備
指定対象は家電製品(テレビ、エアコン、パソコンなど)、自動車、金属製家具、飲料容器(ペットボトル、缶)、小型二次電池、建設副産物(土砂やコンクリートがら)など多岐にわたります。

お役立ち資料
PDFで詳しく見る
2. 企業が取り組むべき3Rと守るべきルール
企業は3Rの考え方を取り入れることで、環境保全と資源循環の両立を図ることが求められます。ここでは企業が取り組むべき3Rの具体的な内容と、資源有効利用促進法に基づくルールや制度についてわかりやすく解説します。
企業が取り組むべき3R
3Rとは、環境負荷の低減と資源の有効活用を目的とした基本的な考え方で、企業にとっても重要な取り組みです。
「リデュース(廃棄物削減)」「リユース(再使用)」「リサイクル(再資源化)」を通じ、環境負荷と廃棄物量の抑制を目指す取り組みです。資源有効利用促進法は、3Rを企業活動へ制度的に組み込むことで、各事業者による循環型社会への貢献を促しています。具体的な取り組みは以下のとおりです。
- リデュース:廃棄物の発生そのものを減らすこと(例:過剰包装の削減、省資源化)
- リユース:一度使ったものを繰り返し使うこと(例:再利用可能な容器の導入)
- リサイクル:使い終わったものを資源として再生利用すること(例:廃プラスチックの再資源化)
3Rの推進によって企業は環境への負荷を減らし、循環型社会の実現に貢献できます。さらに、廃棄物を減らすことでコスト削減につながるほか、環境への配慮を示す企業として社会的信頼や企業イメージの向上に寄与します。
企業が守るべきルール
また本法は政令で対象とする業種・製品を定め、省令で企業に以下のような対応を義務付けています。
- 製品の設計段階で長寿命化・修理や部品共通化を配慮
- 使用者向けに識別表示(素材や分別方法)を義務付け
- 対象製品の自主回収・リサイクル体制の構築と報告
| 対象 | 内容 | 適用企業 |
|---|---|---|
| 特定省資源業種 |
|
紙・製鉄・自動車製造など |
| 特定再利用業種 |
|
建設・複写機・ガラス容器など |
| 指定省資源化製品 |
|
家電・自動車・パソコンなど |
| 指定再利用促進製品 |
|
家電・金属製家具・浴室ユニットなど |
| 指定表示製品 |
|
ペットボトル・缶・塩化ビニル製建設資材など |
| 指定再資源化製品 |
|
パソコン・小型二次電池 |
| 指定副産物 |
|
建設土砂・電気業の石炭灰・コンクリートの塊、木材など |

お役立ち資料
PDFで詳しく見る
3. 資源有効利用促進法の改正内容
資源有効利用促進法の改正により、「脱炭素」「循環経済(サーキュラーエコノミー)」という新たな視点が制度に組み込まれました。ここでは最新の改正内容について、企業が押さえておくべきポイントを紹介します。
改正の背景
2023年に成立した「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(GX推進法)」では、2050年までに温室効果ガスの排出量を実質的にゼロにするカーボンニュートラルの実現と経済成長の両立を目指すGX(グリーントランスフォーメーション)を推進しています。
その柱の一つとして、資源有効利用促進法による、循環経済の推進強化が位置付けられています。今回の改正では、資源の循環利用を促進し、廃棄物の削減を目的とした欧州の法規制、サーキュラーエコノミー規制を踏まえながら、循環経済への転換が議論され、本法の改正案が閣議決定されました。
資源有効利用促進法は3Rの取り組みを目的とした法律ですが、今回の改正案では3Rの取り組みを通じて脱炭素化を図る観点も盛り込まれています。
資源有効利用促進法に関する一部改正のポイント
資源有効利用促進法の改正にはいくつかの項目があります。ここではそれぞれのポイントと、今回の改正により得られるメリットを紹介します。
再生資源利用の義務化
指定された製品(プラスチック製品、電池、建設資材など)を製造する一定規模以上の事業者は、再生資源や再生可能資源の利用に関する目標を定めた計画を作成し、その実施状況を国に報告することが義務付けられます。
-
資源の安定的確保
国内での資源循環が促進されることで、海外資源への依存が低減され、資源価格の変動リスクを抑えることが期待されます。 -
再生技術の促進
企業の再生資源利用への取り組みが本格化し、より高品質な再生材を生み出す技術や、それを利用した製品開発が活発になることが期待されます。 -
環境負荷の低減
廃棄物の削減と天然資源の消費抑制に直接的に貢献し、持続可能な社会の実現に近づきます。
環境配慮設計認定制度
製品の設計段階から資源の有効利用や長寿命化を促すため、優れた「環境配慮設計(エコデザイン)」が施された製品を国が認定する制度が創設されます。
-
環境企業の価値向上
認定を受けることで、環境に配慮した企業であることを具体的にアピールでき、ブランドイメージや市場での競争力向上につながります。 -
消費者のかしこい製品選択を支援
消費者は、認定マークなどを通じて環境に良い製品を容易に識別でき、かしこい選択がしやすくなります。 -
「長く使う」文化の醸成
製品の長寿命化が進むことで、頻繁な買い替えが不要となり、結果的に消費者の経済的負担の軽減や廃棄物の削減に貢献します。
GXに必要な再資源化事業者の特例措置
使用済み小型家電や電気自動車(EV)用バッテリーなど、GX(グリーントランスフォーメーション)の実現に不可欠な製品の回収・再資源化を促進するための特例措置です。高い回収目標を掲げた事業者は、規制が緩和され、より迅速に事業を展開できます。
-
希少資源の国内循環
これまで海外に流出または埋立処分されていた希少金属(レアメタル)などの回収が進み、国内での安定的なサプライチェーン構築に貢献します。 -
リサイクル事業の活性化
規制が緩和されることで、多様な事業者がリサイクル市場に参入しやすくなり、新たな技術やビジネスモデルの創出が期待されます。 -
カーボンニュートラルへの貢献
製品の再資源化は、新規に資源から製造する場合に比べてエネルギー消費を大幅に抑制でき、CO2排出量の削減に直結します。これにより、国全体のカーボンニュートラル目標の達成に貢献します。
サーキュラーエコノミーコマース促進
製品を「所有」するのではなく、「利用」するシェアリングサービスやリペアサービス、サブスクリプションといった循環型ビジネスの健全な発展を促すためのルールが整備されます。
-
「所有から利用へ」の転換
モノを所有することにこだわらず、必要な時にサービスとして利用する消費スタイルが社会に浸透し、大量生産・大量消費型の経済からの脱却を後押しします。 -
「循環型ビジネス」の加速
シェアリングやリペアなど、モノを長く、繰り返し活用するサービスが新たな成長分野として注目され、経済の活性化や雇用の創出につながる可能性があります。 -
市場の信頼性向上
事業者が守るべき基準が明確になることで、サービスの品質や安全性が担保され、消費者が安心して利用できる市場環境が整備されます。

お役立ち資料
PDFで詳しく見る
4. 資源有効利用促進法違反時の罰則
「資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法)」は、3R(リデュース、リユース、リサイクル)を推進するため、事業者に対して製品の識別表示や自主回収・再資源化の仕組み作りなどを義務付けています。
この法律上の義務に違反した場合、国は事業者に自主的な改善の機会を与えるため、直ちに罰則を科すのではなく、段階的な措置を講じます。
-
ステップ1.指導・助言
まずは主務大臣(経済産業大臣または環境大臣)から、違反の是正に向けた指導や助言が行われます。 -
ステップ2.勧告
是正が見られない場合、「判断の基準」に照らして勧告が出されます。対象は、生産量等が一定規模以上の事業者です。 -
ステップ3.企業名の公表
勧告にも従わない場合、企業名が公表される可能性があります。これにより社会的信用の低下を招くおそれがあります。 -
ステップ4.関係審議会の意見
審議会は議論を経て、命令を発動すべきかの意見を主務大臣に意見を答申します。 -
ステップ5.命令
関係審議会の意見も踏まえたうえで、改善が見られない場合、主務大臣から命令が出されます。命令に違反した場合、罰則の対象となります。
罰則の適用:命令や報告義務の不履行があった場合には、以下の罰則が科されます。
- 計画の提出や報告を怠った場合:20万円以下の罰金
- 命令に違反した場合:50万円以下の罰金
上記のように資源有効利用促進法は段階的な是正措置を経たうえで、法的制裁が科される仕組みが採られています。また、法人の代表者または従業員が違反行為をした場合は、違反者本人だけではなく、法人も罰則の対象です。違反による企業イメージの毀損や行政対応コストの増大を回避するためにも、日頃から法令に準拠した運用体制の構築が求められます。

お役立ち資料
PDFで詳しく見る
5. 建設工事における発注者・受注者の責任
資源有効利用促進法において、建設業は「特定再利用業種」の一つとして位置付けられています。また建設工事では大量の資材が使用されると同時に、コンクリートがらや建設汚泥、木くずなどの「建設副産物」が多量に発生するため、その適正な管理と再資源化が社会的課題とされています。
資源有効利用促進法のもとでは、発注者と受注者の双方に3R推進の役割が求められています。
まず、発注者の主な責任は、工事の設計・発注段階から副産物の発生抑制や再利用を念頭に置くことが求められており、副産物の分別や処理方針を仕様書や契約書で明示することです。これにより、現場での分別・回収が円滑におこなえる体制を整備が可能となります。
一方、受注者(施工業者)には、実際の工事において副産物の適正な処理や、再資源化の実施が義務付けられています。また、廃棄物の分別回収・再資源化に加え、実績の記録・報告も求められ、違反があれば法的な指導対象となる場合もあります。
これらの責任分担は、国土交通省が定める「建設副産物対策要領」にも明記され、発注者責任の明確化と再資源化率の向上を目的としています。
今後、建設業界にはサーキュラーエコノミーの流れの中で、資材選定・設計段階からの環境配慮や、副産物を「廃棄物」ではなく「資源」として活用する視点がより一層求められるでしょう。

お役立ち資料
PDFで詳しく見る
関連するお役立ち資料のダウンロード