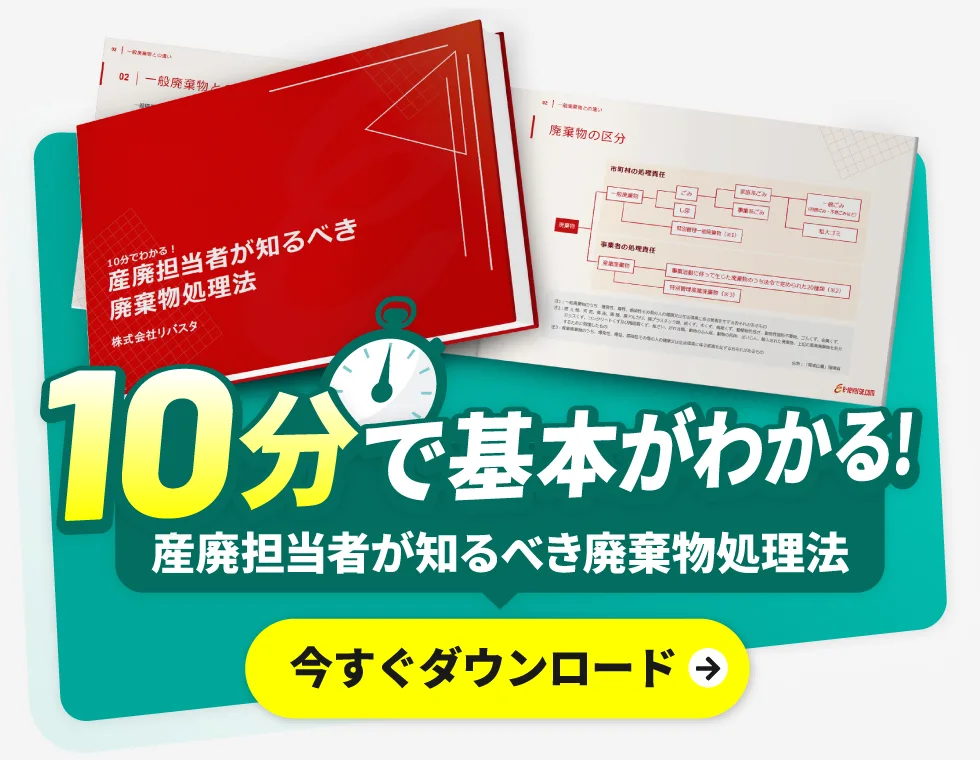近年、都市再開発や大規模インフラ工事、災害復興に伴う建設工事の増加により、膨大な建設発生土(いわゆる残土)が発生しています。残土の処理方法をめぐっては、違法や不正な処理により、崩落事故や環境破壊などさまざまな社会問題も発生しています。本記事では、残土の種類や産業廃棄物との違い、残土の処分方法などについて詳しく解説します。

お役立ち資料
「産廃担当者が知るべき廃棄物処理法」を1冊にまとめました
新しく産廃担当者となった方向けに、廃棄物処理法を中心に知っておくべきことを簡単に紹介します。
PDFで詳しく見る
0. この記事はこんな読者におすすめ
- 残土とは何か、また残土の種類について知りたい方
- 残土と産業廃棄物の違いが分からない方
- 残土処分の方法とルールを知りたい方

お役立ち資料
PDFで詳しく見る
1. 残土(建設発生土)とは何か
残土(ざんど)とは正式名称を「建設発生土」といい、建設工事や土木工事で発生する建設副産物のうちの一つです。建設現場において掘削や配管の埋設などを行った際に発生した土は、構造物の完成後に埋め戻されますが、それでも余剰となり現場外に運び出された土が残土です。残土は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃棄物処理法)に規定される産業廃棄物には該当しません。ただし、金属くずやコンクリートくず、木材や有害物質など、産業廃棄物に該当するものが混入している場合は、それらを除去しなければ、産業廃棄物に該当します。
残土は、国土交通省が省令によって指定副産物に定められており、埋め立てや盛り土などにおける再生資源として、リサイクル活用が積極的に推進されています。

お役立ち資料
PDFで詳しく見る
2. 残土の種類と特徴
残土は、コーン指数(地盤強度の指標で、数値が小さいほど軟弱)、土質材料の工学的分類(粒径や液性による分類)、含水比(水分量が多いほど不安定)、掘削方法の4つの基準により第1種から第4種および泥土の計5種類に分類されます。この分類により、各残土の土質特性に応じた有効利用方法や適切な処理方法を選択することが可能となります。
以下では、残土の種類と特徴、主な利用用途を説明します。
-
第1種建設発生土
主に粒の大きさが2㎜以上の礫(れき)や砂で構成された礫質土(れきしつど)や砂質土(さしつど)で、コーン指数は特に定められていません。第1種建設発生土は、礫や砂に砂よりも細かい細粒が混じる割合が少なく、粒がそろっており、大部分が礫や砂である土質です。水はけが良く、適切な締固めをすることが可能で、地盤強度が高いため、建築物の埋め戻し、道路用盛土、鉄道や空港の盛土など、幅広い用途で有効に活用されます。 -
第2種建設発生土
コーン指数は800kN/㎡以上が必要です。第1種建設発生土と同様に、主に礫や砂で構成されていますが、第1種建設発生土と比べて、砂より細かい細粒の混じる割合が大きい土質です。砂や細かい細粒が増えると、圧力や振動に不安定になるため、礫の大きさや砂の割合などに注意が必要ですが、第1種建設発生土と同様、建築物の埋め戻しなど強固な地盤を必要とする用途にも利用可能です。 -
第3種建設発生土
コーン指数は400kN/㎡以上が必要です。主な構成は、細粒の割合が大きい砂や粘性のある粘性土(ねんせいど)で、含水比は40%程度以下とされます。特に粘性土は水分の影響を大きく受けやすく、水分を含むと地盤沈下の原因になる場合があります。再利用にあたっては、施工機械の選定に注意が必要ですが、通常の施工が可能な程度の粘性土であることが前提となります。河川の堤防、土地の造成などに利用可能です。 -
第4種建設発生土
コーン指数は200kN/㎡以上が必要です。細粒の割合が大きい砂質土や、含水比が40~80%程度の水分量の多い粘性土で、第3種建設発生土に該当しないものです。有機物を含む有機質土(ゆうきしつど)も含まれます。基本的に、水面埋立以外には利用できません。他の用途で利用する場合には、土質改良が必要です。 -
泥土
コーン指数は200kN/㎡未満で、細粒分の多い砂質土や、含水比80%以上のきわめて水分量の多い粘性土、有機質土が該当します。例えば、港湾や河川などの底をさらう浚渫(しゅんせつ)の際に発生する水分を多く含む泥状の残土を指します。そのままでは利用することはできないため、脱水、粘度の調整、安定処理などの土質改良が必要です。

お役立ち資料
PDFで詳しく見る
3. 汚泥などの産業廃棄物との違い
建設工事の現場では、水分を多く含んだ泥状の土や泥水が発生することがあります。これらは、前述した残土の分類における「泥土」に該当しますが、土質改良をおこなう前提で再利用が可能な土で、産業廃棄物には分類されません。一方、建設汚泥は、泥土と同様、掘削工事などで発生する泥状の掘削物や泥水ですが、再利用が難しく産業廃棄物に該当します。
| 泥土 | 建設汚泥 | |
|---|---|---|
| 分類 |
|
建設工事で発生する廃棄物のうちの汚泥産業廃棄物 |
| 主な発生源 |
|
|
| 性状 |
|
|
|
|
|
| 法的規制 | 廃棄物処理法の規制対象外 |
|
| 取り扱い | 「発生土利用基準」で提示された利用用途を元に再生利用が推進 |
|

お役立ち資料
PDFで詳しく見る
4. 残土が引き起こす社会問題とは
残土は、以下にあげるさまざまな社会問題を引き起こしています。
-
危険な盛土による被害発生の問題
違法に建設残土を用いた盛土が崩落し、大規模な土砂災害が発生する事例が各地で報告されています。これにより、人的被害に加え、通行止めや河川への流入など甚大な被害が生じています。 -
違法な残土処分の問題
残土の不法投棄や、産業廃棄物が混入した残土の処分により、雨水による土壌・地下水の汚染、有害物質の浸出、景観の悪化など、さまざまな環境問題が発生しています。 -
残土量の増加の問題
近年、高速道路や鉄道の延伸といった大規模インフラ整備、都市再開発、大規模災害からの復興工事、地下鉄・地下街などの地下開発により、大規模な建設・土木工事が増加しています。特に、深部の地下工事やトンネル工事では、膨大な量の残土が発生しています。 -
残土処分場の不足と受入れ先の確保の問題
残土量の増加にともない、残土処分場の不足が深刻化しています。既存の処分場の容量不足により、遠隔の処分場への運搬が必要となりますが、人的・物的コストの問題、環境への影響などが発生します。また、新たな処分場の建設に必要な近隣住民の合意は、その獲得は困難を極めています。 -
残土処分において危惧される環境問題
残土処分には、土壌汚染のリスク、最終処分場周辺の環境変化にともなう生態系への影響、運搬時のCO2排出、盛土による景観の変化など、環境への影響が危惧されます。

お役立ち資料
PDFで詳しく見る
5. 残土の処分方法と流れ
残土は再生可能資源として利用することが推奨されており、可能な限り再生利用することが求められます。ここでは、残土の処分方法と流れを説明します。
-
処分方法の基本原則
残土の処分方法は、残土の発生量の抑制に努めたうえで、現場内での再利用が原則です。現場内で工作物や建築物の埋め戻しに利用しますが、現場内で利用しても余った残土は、現場外へ搬出し、資源として再利用されます。 -
現場外で処分する場合の、搬出先の明確化ルール
残土を現場外で処分する場合、令和6年6月より、元請業者は残土の最終搬出先までの確認が義務化されました。再生利用先が決まるまでの仮置き場に搬出する場合も確認が必要です。
元請業者に義務化された主な内容は以下の通りです。
- 最終搬出先に至るすべての搬出先に盛土規正法の許可があることを確認すること
- 搬出後に、受け入れ先が確実に残土を受け入れたことを受領書により確認すること
- 一定規模以上の工事では、再生資源利用促進計画や再生資源利用計画を作成すること
-
現場外での処分方法
現場外での処分方法には、以下の選択肢があります。受け入れ先によっては、残土の種類が限られている場合があります。-
他現場への搬出
発生した現場内で利用できない残土を他の現場で再利用する方法です。(現場間利用)
リサイクル率の向上に貢献するとともに、新たな土砂の調達を削減するため環境負荷の軽減にも繋がります。
現場間利用を行う際には搬出元と搬入元の条件(土質、土量、工期など)が一致する必要があり、残土をはじめとする建設副産物情報を利用者間で共有できるコブリス・プラスによる現場間のマッチングが推進されています。 -
ストックヤード(仮置き場)に搬出
建設計画の段階で、再利用先が決まらない場合など、残土の仮置き場であるストックヤードに搬出する方法があります。ストックヤードでは、必要に応じて土質改良が行われ、再利用の用途が拡大する可能性があります。
ストックヤードを利用した場合にも、元請業者は最終搬出先の確認が必要です。ただし、国に登録されたストックヤードに搬出した場合には、登録ストックヤード運営事業者が引き継ぐため、元請業者は最終搬出先までの確認は不要となります。 -
土質改良プラント
残土をリサイクルプラントに搬出する方法もあります。リサイクルプラントは、受け入れた残土をふるいにかけ、土質改良を行った上で、改良土として再利用を可能にする施設です。 -
最終処分場への搬出
建設工事で発生した掘削物や土のうち、コンクリート塊やアスファルト、木材、紙くず、金属くず、ガラスくずなど産業廃棄物にあたる物が混入し、取り除けない場合には、残土処分場に搬出します。再利用できない土などを運び込み、そのまま地面に埋め戻されます。
-
他現場への搬出

お役立ち資料
PDFで詳しく見る
関連するお役立ち資料のダウンロード