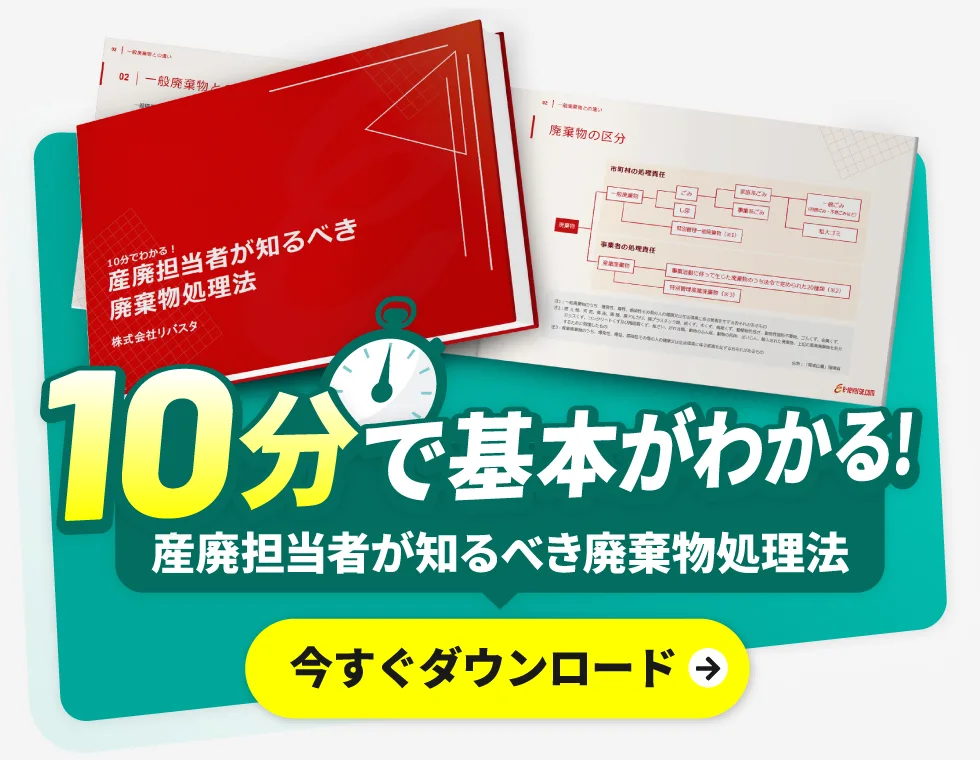コブリス(Construction Byproducts Resource Information interchange System, 建設副産物情報交換システム)をご存じでしょうか。建設現場や解体現場で発生する不要な資材や廃材などを有効活用するためのツールとして、2002年4月に運用が開始されました。コブリスはサービスの提供開始から20年以上が経過したため、より使いやすいサービスを目指して2025年5月に「コブリス・プラス」としてリニューアルされました。アップデートされたコブリス・プラスの機能や特長、旧コブリスとの違い、利用手続きなどを解説します。

お役立ち資料
「産廃担当者が知るべき廃棄物処理法」を1冊にまとめました
新しく産廃担当者となった方向けに、廃棄物処理法を中心に知っておくべきことを簡単に紹介します。
PDFで詳しく見る
目次
0. この記事はこんな読者におすすめ
- コブリス・プラスとは何か知りたい方
- 旧コブリスとの違いを知りたい方
- コブリス・プラスの利用方法・手順を知りたい方

お役立ち資料
PDFで詳しく見る
1. コブリス・プラス(建設副産物情報交換システム)とは
コブリス・プラスとは、一般財団法人 日本建設情報総合センター(JACIC)が運用する、建設副産物(余剰資材や廃材など)および建設発生土を有効活用するための情報交換システムで、主に以下の情報管理が可能です。
- 建設リサイクル法など各種法令に対応する帳票の作成と提出
- 建設副産物実態調査や公共工事土量調査に使用するデータの登録や取りまとめ
- 建設副産物や発生土の搬出入計画を検討する際の支援
また、国土交通省が運用してきた「建設発生土の官民有効利用マッチングシステム(官民マッチング)」の機能も引き継がれています。これは、建設現場で発生した不要な建設発生土を処分したい事業者と、土を必要とする他の事業者とをマッチングし、有効活用を促進するためのシステムです。

お役立ち資料
PDFで詳しく見る
2. 旧コブリスとの違い
旧コブリスは「建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)」に定められた建設副産物の届け出や計画書・実施書、実態調査(センサス)のための帳票作成などをサポートし、工事発注者、排出事業者(建設工事の施工者等)および処理事業者(再資源化施設等)の間で情報交換を行うシステムでした。
一方、建設発生土の有効活用を支援する「建設発生土情報交換システム」や「建設発生土の官民有効利用マッチングシステム」が旧コブリスとは別に運用されてきました。コブリス・プラスは、これらのサービスをすべて統合することで、建設副産物の情報管理に加えて、発生土の情報管理と需給のマッチングを可能とする建設リサイクルの総合システムとして生まれ変わりました。

お役立ち資料
PDFで詳しく見る
3. コブリス・プラスの機能・特長
コブリスは建設リサイクル法に基づいた情報交換システムとして2002年から運用されてきましたが、書類作成やデータ集計支援のための「建設リサイクルデータ統合システム(CREDAS=クレダス)」の機能が2018年に追加されています。また、2025年5月にコブリスに先駆けて運用されてきた「建設発生土情報交換システム」と「建設発生土の官民有効利用マッチングシステム」の機能が追加され、新たにコブリス・プラスとして運用が開始されました。
コブリス・プラスの主な機能
- 工事発注者、排出事業者(建設工事の施工者等)、処理事業者(再資源化施設等)間のリアルタイムな情報交換
- 建設リサイクル法など各種法令に対応する帳票の作成および提出の支援
- 建設副産物実態調査(センサス)や公共工事土量調査用データの取りまとめと共有
- 建設副産物や発生土の搬出・搬入計画の検討支援
コブリス・プラスの主な特長
- 旧コブリスと建設発生土システムを一体化
- 発注者と受注者間を横断する確認・修正作業などの業務フロー
- チェックリストによる登録前のデータ確認でデータ精度を向上
ほかにも、建設発生土のリアルタイムなマッチング機能や地図連携機能によるルート表示などの特長があります。
建設副産物(建設発生土)マッチング・リアルタイム情報共有機能
建設発生土を出す側は、建設発生土の量、土質、発生時期、搬出場所などの情報をシステムに登録します。公共工事だけでなく、民間工事に関する情報も登録可能です。発生土を受け入れる側は、建設発生土を受け入れたい工事現場や、受け入れ可能な仮置き場などの情報をシステムに登録します。受け入れ場所のほか、必要な土量、土質、搬入時期などの情報が登録できます。
システムに登録されたこれらの情報の中から、それぞれのニーズに合致する相手を検索し、絞り込みができます。その際、地図上で工事現場や受入施設の位置を確認しながら、地理的に近い相手を探すことができる地図検索や、土質、発生時期、必要量/供給量、距離など詳細条件による検索などを活用することでリアルタイムなマッチングが可能です。
建設副産物の搬出先検索機能(地図連携によるルート表示)
コブリス・プラスでは、建設副産物や発生土の搬出先を地図上に表示して走行ルートや距離、所要時間などを確認することができます。建設副産物の処理施設や建設発生土の受け入れ先など、複数の搬出先候補の位置を地図上に表示できるため、近い場所にある最適な搬出先を容易に選択できます。

お役立ち資料
PDFで詳しく見る
4. 事業者のメリット
コブリス・プラスは従来のコブリスが持つ機能に加え、建設発生土情報交換システムおよび建設発生土の官民有効利用マッチングシステムの利点も継承しています。これにより、工事発注者、排出事業者、処理業者それぞれに以下のようなメリットがあります。
工事発注業者のメリット
工事発注者(国や自治体、民間企業など)
-
提出書類の確認作業が簡素化される
受注者との紙の資料や電子メールでのやりとりが不要になり、システム上で確認が可能になります。 -
登録されたデータチェックの精度向上と効率化
受注者が登録したデータをチェックリストで確認でき、修正依頼や確認完了の連絡もシステム上から行えます。 -
簡易センサス(受注者の実態調査)の精度向上と効率化
調査票の回収と取りまとめ、確認作業がシステム上でおこなえます。 -
建設副産物の状況をリアルタイムで把握可能
登録データの集計やリサイクル率の簡易集計ができるので、建設副産物の発生と利用の状況がリアルタイムで把握できます。
排出事業者のメリット
排出事業者(施工業者、解体業者など)
-
提出書類の確認作業が簡素化される
建設リサイクル法に定められた再生資源利用計画書・実施書作成の負担が軽減されます。 -
登録されたデータチェックの精度向上と効率化
データ登録時に誤りがある場合は、チェックリスト上でエラーや警告メッセージが表示されるのでわかりやすく確実に登録できます。 -
簡易センサス(受注者の実態調査)の精度向上と効率化
従来は報告書の書式やチェックリストをダウンロードして記入、確認作業を行っていましたが、システム上で作成・確認・提出が可能となっています。修正作業・再提出もシステム上で行えます。 -
現場掲示資料を容易に作成可能
省令に定められた現場掲示様式に必要事項を記入・出力できるので、現場掲示資料の作成が効率化されます。
処理業者のメリット
処理業者(リサイクル施設、再生資材販売業者など)
-
登録・更新料が無料
自社の情報を無料で登録でき、建設副産物排出事業者による検索対象となります。 -
自社施設の所在地がシステムの地図上に表示される
排出事業者が副産物のリサイクル施設を検索する際に地図上で表示されます。 -
自社施設のPRになるので新規取引先の開拓につながる
事業所の概要に加え、処理対象の詳細や処理能力、受入料金、実績などを登録可能であり、自社のPRにつながり、新規取引先の獲得が期待されます。

お役立ち資料
PDFで詳しく見る
5. コブリス・プラスの利用手続き
コブリス・プラスの利用手続きは事業者ごとに異なります。また、官民マッチングの利用には別途手続きが必要です。なお、旧コブリスの事業者IDや登録情報はコブリス・プラスに引き継がれているため、継続して利用することができます。
発注者の利用手続き
- コブリス・プラスの利用申込画面で「発注者」をクリックします。
- 「ご登録されるメールアドレス」欄にシステムで使用するメールアドレスを入力し「認証コードを発行する」をクリックします。すると、登録したメールアドレスに「認証コード」が記載されたメールが届きます。
- 「メール記載の認証コードを入力してください。」の画面に移りますので「認証コード」欄に「認証コード」を入力し、「申込を続ける」をクリックします。その後、「■ 新しいユーザー(発注機関)のお申込み」画面に遷移します。認証コードの有効期限は発行から2時間です。
- 契約内容、発注機関、契約担当者などの設定内容を入力し、「利用規約」をクリックして内容を確認したら「利用規約へ同意する」にチェックを入れます。
- 「入力内容を確認する」をクリックすると確認画面が表示されます。入力内容に誤りがなければ「この内容で申し込む」をクリックして申し込みは完了です。
受注者、処理業者の利用手続き
受注者と処理業者の利用申し込みも、利用申込画面で「受注者」または「処理業者」をクリックした後は、基本的に発注者と同様の手順となります。ただし、旧コブリスを利用していた受注者は、「コブリスを使ったことがありますか?」の設問で「はい」を選択し、旧コブリスで使用していたユーザーIDを入力します。
また、受注者が建設許可を受けている場合は許可番号を6桁で入力しますが、許可番号が6桁未満の場合は許可番号の先頭に「0」を追加して6桁にしてください。許可番号が4桁の場合は0を2つ追加します。
以上がコブリス・プラスの利用手続きです。建設リサイクル法を遵守し、建設副産物や発生土を適切に有効活用するために、コブリス・プラスの活用が推奨されます。

お役立ち資料
PDFで詳しく見る
関連するお役立ち資料のダウンロード