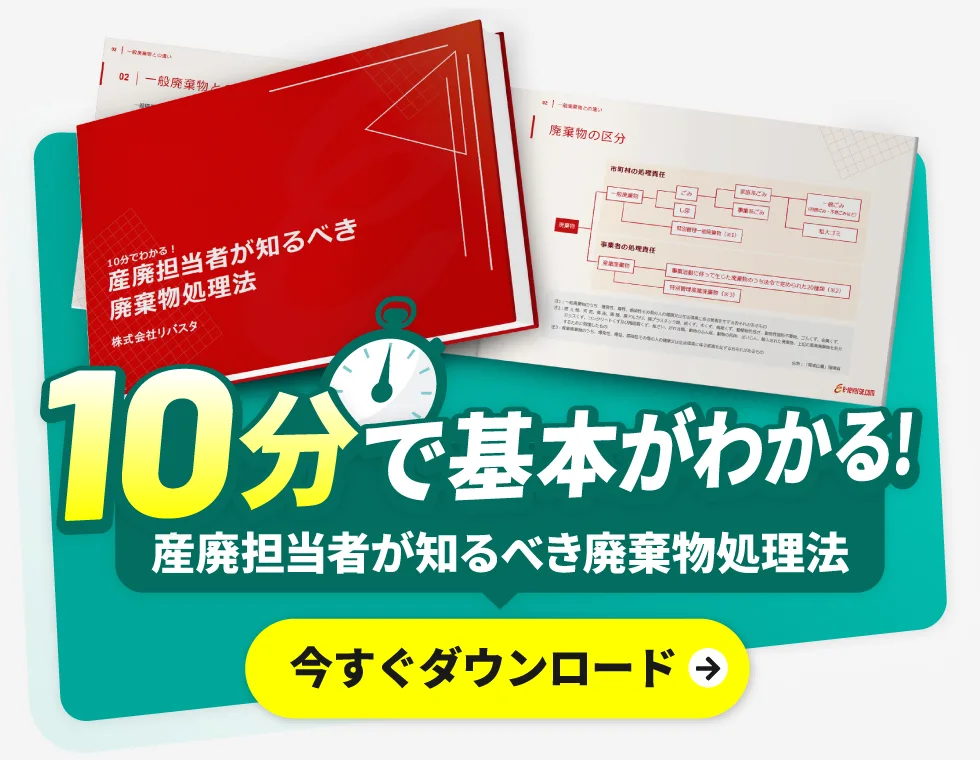建設工事で発生する廃棄物の増加による問題を受けて制定された「建設リサイクル法」では、特定の建設資材に対して「分別解体」や「再資源化」が義務付けられています。ここでは、建設リサイクル法の内容や要件、手続きの流れ、罰則などについて、詳しく解説していきます。

お役立ち資料
「産廃担当者が知るべき廃棄物処理法」を1冊にまとめました
新しく産廃担当者となった方向けに、廃棄物処理法を中心に知っておくべきことを簡単に紹介します。
PDFで詳しく見る
目次
0. この記事はこんな読者におすすめ
- 建設リサイクル法の概要を知りたい方
- 建設リサイクル法の対象資材や工事について知りたい方
- 建設リサイクル法に違反した場合の罰則について知りたい方

お役立ち資料
PDFで詳しく見る
1. 建設リサイクル法とは
建設リサイクル法とは、正式名称を「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」といい、2000年5月31日に制定され、2002年5月30日に本格的に施行されました。
建設リサイクル法が制定された背景には、廃棄物の発生量が増え続け、最終処分場の不足や不適切な処理など、廃棄物処理に関する課題が深刻化したことが挙げられます。さらに、昭和40年代に建てられた建築物の老朽化により、建設廃棄物の増加も見込まれるなか、資源の有効活用を目的として、建設現場などから発生する廃棄物の再資源化を図るために制定されました。
この法律では、特定の建設資材に対して「分別解体」や「再資源化」が義務付けられており、適切な対応が行われるよう、解体業者の登録制度や工事着手前の届出、さらには発注者と受注者の間での書面での説明や契約に関するルールなどが定められています。

お役立ち資料
PDFで詳しく見る
2. 建設リサイクル法の対象資材
建設リサイクル法において、分別解体や再資源化が義務付けられている「特定建設資材」は以下の4種類です。
- コンクリート
- コンクリート、及び鉄から成る建設資材
- アスファルト・コンクリート
- 木材(建築物の解体などにより生じたもの。繊維板などを含む)
なお、木製コンクリート型枠などのリース材は、現場で使われている間は建設資材とみなされますが、使用後にリース会社へ返却される場合は、建設資材廃棄物とならず、分別解体・再資源化の対象外になります。

お役立ち資料
PDFで詳しく見る
3. 建設リサイクル法の対象工事
建設リサイクル法の対象となる建設工事は、次のとおりです。対象の建設工事となるかについて確認しておきましょう。
- 建築物の解体工事:床面積の合計80㎡以上の「建築物の解体工事」
- 床面積の合計500㎡以上の「建築物の新築・増築工事」
- 請負金額1億円以上の「建築物の解体・新築・増築以外の、建築物の修繕・模様替え(リフォームなど)の工事)」
- 請負金額500万円以上の「建築物以外の工作物の解体工事又は新築工事等」

お役立ち資料
PDFで詳しく見る
4. 対象工事の手続き
建設リサイクル法に基づき、対象となる工事を実施する場合、発注者は工事着手の7日前までに、都道府県知事に分別解体等の計画書などを届け出る必要があります。手続きの流れは以下の通りです。
説明
対象建設工事を請け負う受注者は、発注者に対して建築物などの構造、工事着手の時期、工程の概要、分別解体等の計画などについて、書面を交付して説明します。
契約
発注者が受注者と交わす契約書面に、分別解体などの方法や解体工事に必要な費用、再資源化などに必要な費用、再資源化を行うための施設の名称や所在地などを明記する必要があります。
届出
対象建設工事の発注者は、工事着手の7日前までに、都道府県知事に分別解体計画書やその他必要な書類を提出します。
告知
受注者が工事を他の建設業者に再委託する場合は、その業者に対し、対象工事に関して発注者から通知された内容を適切に告知する必要があります。
工事の実施
工事に着手します。行政庁などは、工事の適正な実施を確保するために必要があると認めた場合、受注者に対して、必要な助言・勧告、命令、立入検査、報告の徴収などを行う場合があります。
完了報告
工事完了後、受注者は分別解体・再資源化を基準に従って実施したことを、書面で発注者に報告します。また、リサイクルの実施記録を作成・保存する必要があります。

お役立ち資料
PDFで詳しく見る
5. 建設リサイクル法違反時の罰則
建設リサイクル法は、廃棄物の適正な処理と資源の有効活用を目的として制定されており、違反した事業者に対して罰則を科すことで、法令の遵守を促しています。罰則の内容は、違反の度合いによって異なり、過料や罰金、さらには懲役刑が科される場合もあります。分別解体等・再資源化等・解体工事業などによって罰則が細かく分かれているため、事前に確認しておきましょう。
分別解体などの実施における罰則
建物を解体する際の分別解体は、リサイクルの基本です。適正なリサイクルを確保し、環境への影響を最小限に抑えるため、ルールに違反した場合は厳しい罰則が科せられます。
工事の届出は、行政が工事の実態を把握するために重要なものであり、届出を怠ったり、虚偽の届出をしたり、変更を届け出なかったりすると、20万円以下の罰金が科されます(51条1号)。
また、県知事から届出内容の変更を命じられたにもかかわらずに従わない場合は30万円以下の罰金(50条1号)、分別解体を命じられたのに従わなかった場合は、50万円以下の罰金(49条)と、重い罰則が科せられる可能性があります。
再資源化などの実施における罰則
解体した資材を再資源化することは、リサイクルの完結に不可欠です。分別された資源が確実にリサイクルされるためにも、違反した場合は罰則が科せられます。
建設リサイクル法では、建設工事における資材の再資源化が完了した際に、受注者は書面で発注者に報告し、実施状況を記録して保存することが義務付けられていますが、発注者への報告を怠ったり、記録を残さなかったりした場合は、10万円以下の過料となります(53条1号)。
また、県知事から再資源化の実施を命じられたにもかかわらず従わない場合は、50万円以下の罰金が科せられます(49条)。
解体工事業における罰則
解体工事業においても、適正な解体工事の実施や安全性を確保するため、法律によってさまざまな義務と罰則が設けられています。
行政が事業者の正確な情報を把握するために必要な事業者の登録内容に変更があったにもかかわらず、変更届を出さなかったり、虚偽の申請を行ったりした場合には30万円以下の罰金(50条2号)、廃業などの届け出を怠った場合には10万円以下の過料(53条2号)が科せられます。登録が失効したことを速やかに発注者に通知しなかった場合は、20万円以下の罰金となります(51条2号)。
また、無登録や更新を行わずに営業を行った場合(48条1号)、行政からの業務停止命令に反して事業を継続した場合(48条3号)には、適正な工事の実施を確保できない観点から、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金といった重い刑事罰が科されます。
他にも、安全管理や情報公開の観点から、技術管理者の未選任は20万円以下の罰金(51条3号)、標識の不掲示(53条3号)、帳簿の不備(53条4号)といった違反は10万円以下の過料が科されます。さらに知事などへの報告義務の不履行や虚偽報告(51条4号)、立入検査の妨害などの行政監督を妨げる違反(51条5号)は、20万円以下の罰金が科せられます。

お役立ち資料
PDFで詳しく見る
関連するお役立ち資料のダウンロード